こんにちは!FLOW会計事務所の森です。
今回は相続税の税務調査や正しい申告の重要性についてご紹介いたします!
■ 相続税の税務調査はいつ行われるのか
相続税の申告が終わってから、「1年半から2年半の間」に税務調査が行われる可能性が高いとされています。
ただし、過去に申告内容に問題があった方や、大きな財産移動があった方など、特に疑義が持たれるケースは別です。あらかじめ「うちは調査が入りそうだな」と感じる部分があれば、提出書類や領収書、通帳のコピーなどをしっかり整理しておきましょう!
■ 税務調査でチェックされやすいポイント
1.生前贈与の有無
相続税の調査では、生前贈与が行われていたかが重点的に調べられます。
故人(被相続人)から相続人、または親族へ資金移動している履歴がないか、相続人全員の銀行口座を細かく確認されます。贈与を受けていたにもかかわらず申告していない場合、追徴課税や重加算税のリスクが高まります。故意に隠したと認定されると、「単なる申告漏れ」ではなく「不正」とみなされ、重加算税(※)が課される可能性があります。
贈与があった場合は、「最初から正直に申告しておくこと」が重要です!
※重加算税は、「意図的に隠そうとした」と認められた場合に適用される、非常に重いペナルティです。
2.名義預金の有無
「名義預金」とは、実際には故人が管理していたにもかかわらず、子供や孫の名義で預金口座が作られているケースを指します。
税務調査官は、口座開設時の書類や印鑑の使用履歴、筆跡などを徹底的に調べ、誰が実質的に管理していたかを判断します。名義預金と判断された場合は、相続財産として計上され、申告漏れ扱いとなります。
3.申告漏れを防ぐ
先述しましたが、申告漏れが見つかると、追徴課税だけでなく重加算税が課される恐れがあります。
相続税は複雑なルールが多いため、相続税の扱いに慣れた税理士や会計事務所に依頼することで、適切な申告を行い、リスクを最小限に抑えられます。相続税の専門家に相談することが最も重要です!
■ 税務調査対策:会計事務所スタッフの視点
1.書類の整理は早めに
相続が発生した際は、すぐにでも「何がどこにあるか」を洗い出すことが大切です。銀行通帳や明細、契約書などをまとめておくと、税理士への相談もスムーズになります。
2.疑問点は積極的に専門家に確認
「贈与してもらったが、申告していない」「名義預金になるか心配」など、曖昧な点は先延ばしにせず会計事務所や税理士に相談するのがおすすめです。
3.提出期限を絶対に守る
相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。特に相続財産が多い場合や、不動産の評価が複雑な場合は、早めの準備が肝心です。
4.正直ベースで申告する
税務署はあらゆる情報網を駆使し、故人や親族の口座の存在を把握している場合が多いです。隠匿しようとしたり嘘をついたりすると、重加算税を含めた大きなリスクが伴いますので、十分ご注意ください!
■ まとめ
相続税の税務調査は、申告後1年半から2年半の間に入る可能性が高く、そのときに生前贈与の有無や名義預金、不動産の評価などを厳しくチェックされます。申告漏れや虚偽申告が見つかると追徴課税だけでなく、重加算税という重いペナルティが科されることもあります。
また、解約済みの通帳や親族の口座情報までしっかりと調査されるため、「大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。相続税の申告は専門的な知識が求められますし、期限内に正しく申告するためにも、「相続税に強い税理士や会計事務所」に早めに相談されるのが得策です。
私たち会計事務所も、実際に相続税の申告や税務調査の立ち会いを多数経験し、「もう少し準備していれば無用な負担を避けられたのに…」というケースをよく目にしてきました。後々慌てることがないように、ぜひ今のうちから財産や口座情報、各種書類をしっかり整え、相談できる体制を整えていただければと思います。相続はいつ起こるかわからないからこそ、普段からの意識と備えが大切です!!
最後までお読みいただきありがとうございます!



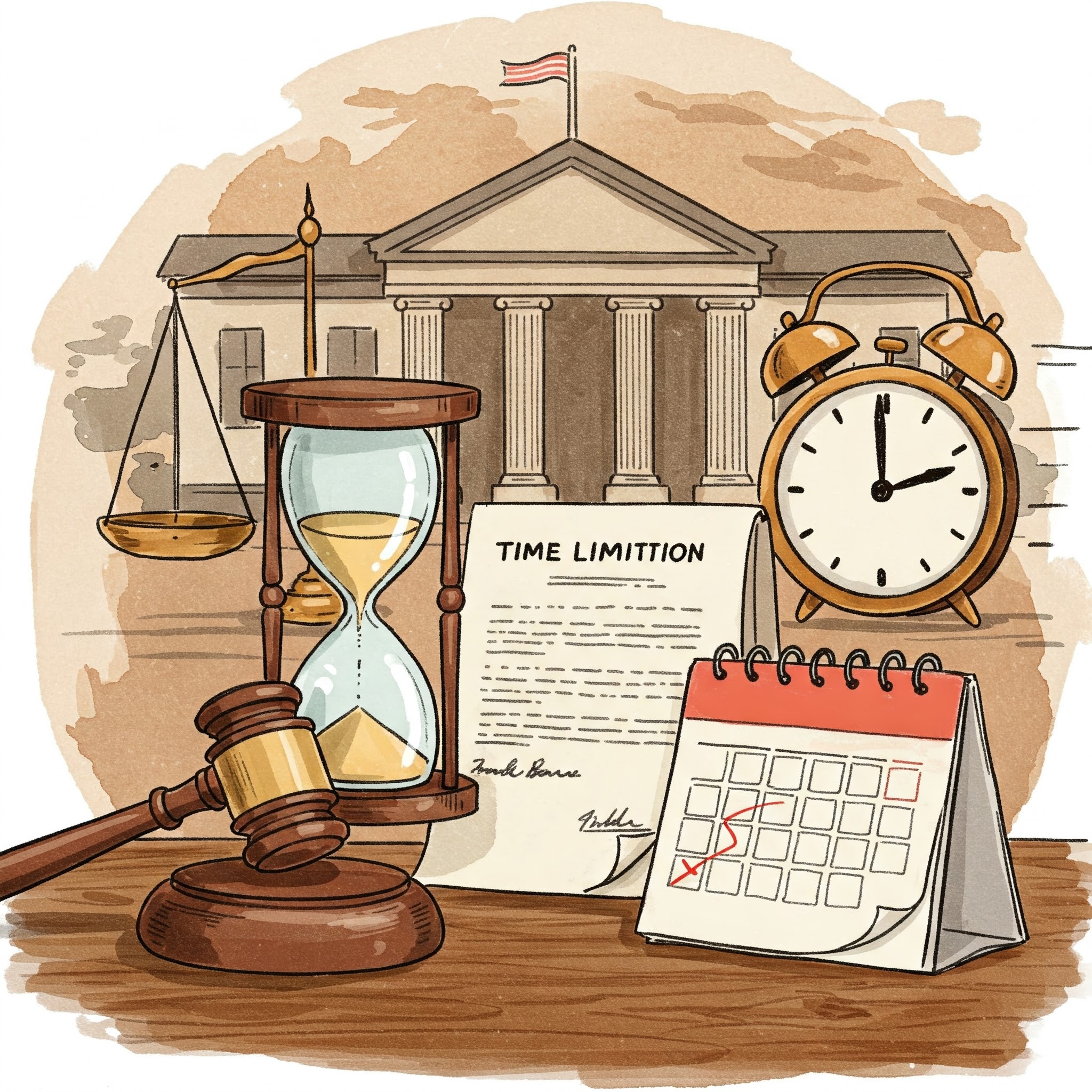
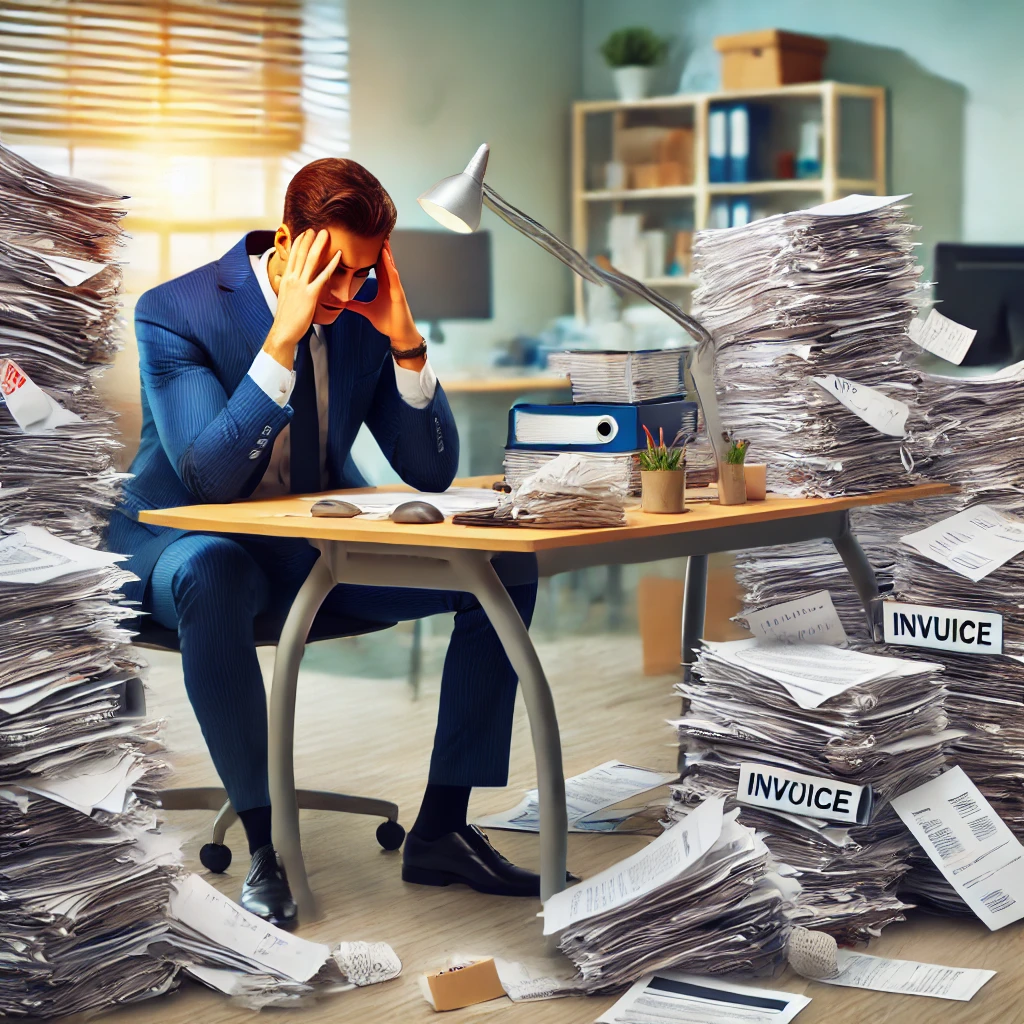




.jpg)