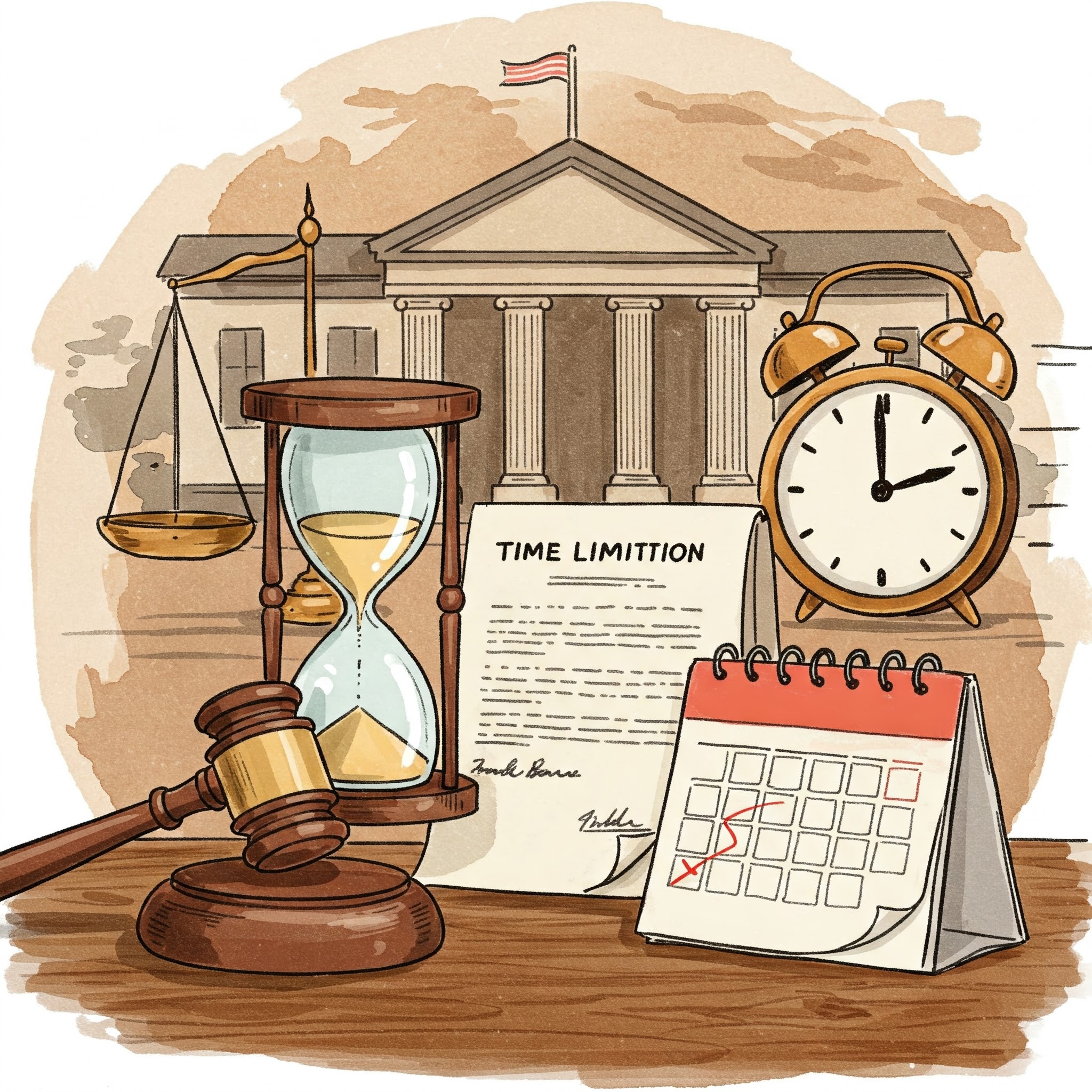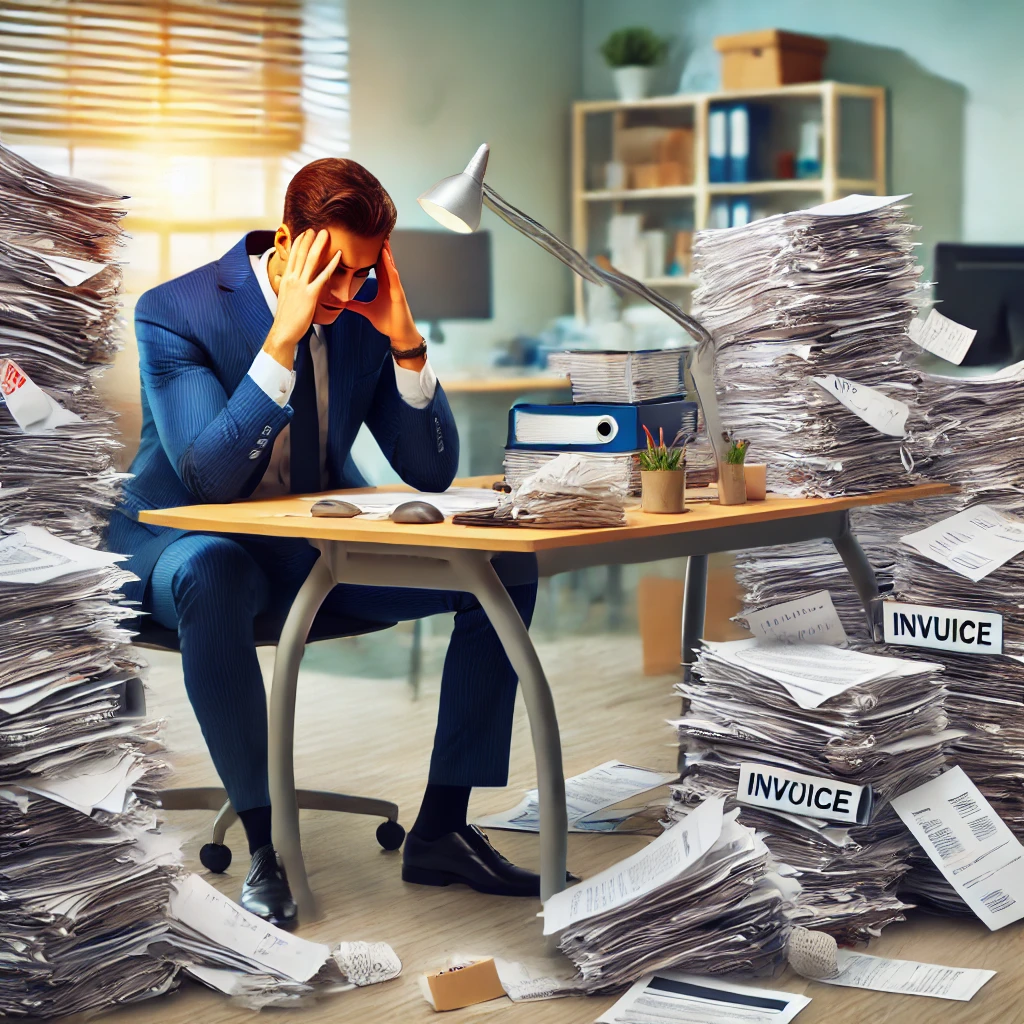こんにちは、FLOW会計事務所の小針です。
今回は、贈与税の時効について解説します。贈与税についてあまり聞き慣れないかもしれませんが、実は、過去に親や祖父母から贈与を受けた場合、一定額を超えると税金が発生することがあります。そこで、「申告していなかったけれど、今さら税務署に指摘されたらどうしよう…」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。今回はその時効に関して、どれくらいで時効が成立するのか、どんな場合に延長されるのかなどを解説します。
1.贈与税の時効は6年
贈与税の時効は原則として 6年 です。つまり、贈与を受けた日からではなく、申告期限の翌日から6年がカウントされます。これが過ぎると、税務署から指摘されることなく、贈与税の申告は不要となります。
具体的に考えてみましょう。たとえば、令和4年10月2日に贈与を受けた場合、その申告期限は翌年の令和5年3月15日です。この場合、時効のカウントは 令和5年3月16日からスタートし、6年後の 令和11年3月16日 に時効が成立します。
2.時効が延長されるケース
ところが、贈与税の申告を意図的にしなかったり、偽りや不正行為があった場合、時効は 7年に延長されます。たとえば、「申告が必要だと知っていながら、わざと隠していた」という場合です。このような悪質な行為には、重いペナルティが課せられる可能性があるので、注意が必要です。
3.贈与日はいつ?
時効を計算する際、贈与が実際に行われた日を正確に特定することが大切です。贈与の方法によって、その日の特定方法も異なります。
現金贈与の場合:「あなたにあげる」と言って現金を渡した日が贈与日です。預金口座に振り込んだ場合も、振り込んだ日が贈与日となります。
書面での贈与の場合:贈与契約書にサインした日が贈与日です。
不動産の贈与の場合:基本的には契約書にサインした日が贈与日とされますが、時効が過ぎてから登記を行うような場合には、登記日が贈与日と見なされることもあります。
4.期限後申告とペナルティ
もし贈与税の申告が必要にも関わらず、期限内に申告しなかった場合にはペナルティが発生します。主なペナルティは以下の通りです。
無申告加算税:期限後に申告した場合、原則として 15% の加算税がかかります。ただし、贈与額が50万円を超える場合は、その超過分に対して 20% となります。
重加算税:故意に税金を逃れようとした場合には、 40% の重加算税が課せられます。さらに、過去に繰り返し無申告加算税などを課された場合は、税率が 50% にアップします。
延滞税:申告期限から2ヶ月を過ぎると延滞税が発生します。延滞税の額は、遅延した期間によって異なります。
5.時効成立後はどうなる?
贈与税の時効が成立すれば、基本的に申告は不要です。時効が過ぎた後に税務署に申告をしても受け付けてもらえません。ただし、不正行為があった場合、時効が成立していても追及される可能性はあるので注意が必要です。
6.まとめ
贈与税については、時効のルールをしっかり理解しておくことが大切です。もし過去に贈与を受けたにも関わらず、申告していなかった場合は、なるべく早く税理士に相談することをおすすめします。税務署から指摘を受ける前に、正しく申告をしておくことが安心への第一歩です。
贈与税に関して不安な点があれば、ぜひご相談ください。初回の相談は無料ですので、気軽にお問い合わせください!
最後までお読みいただきありがとうございました!