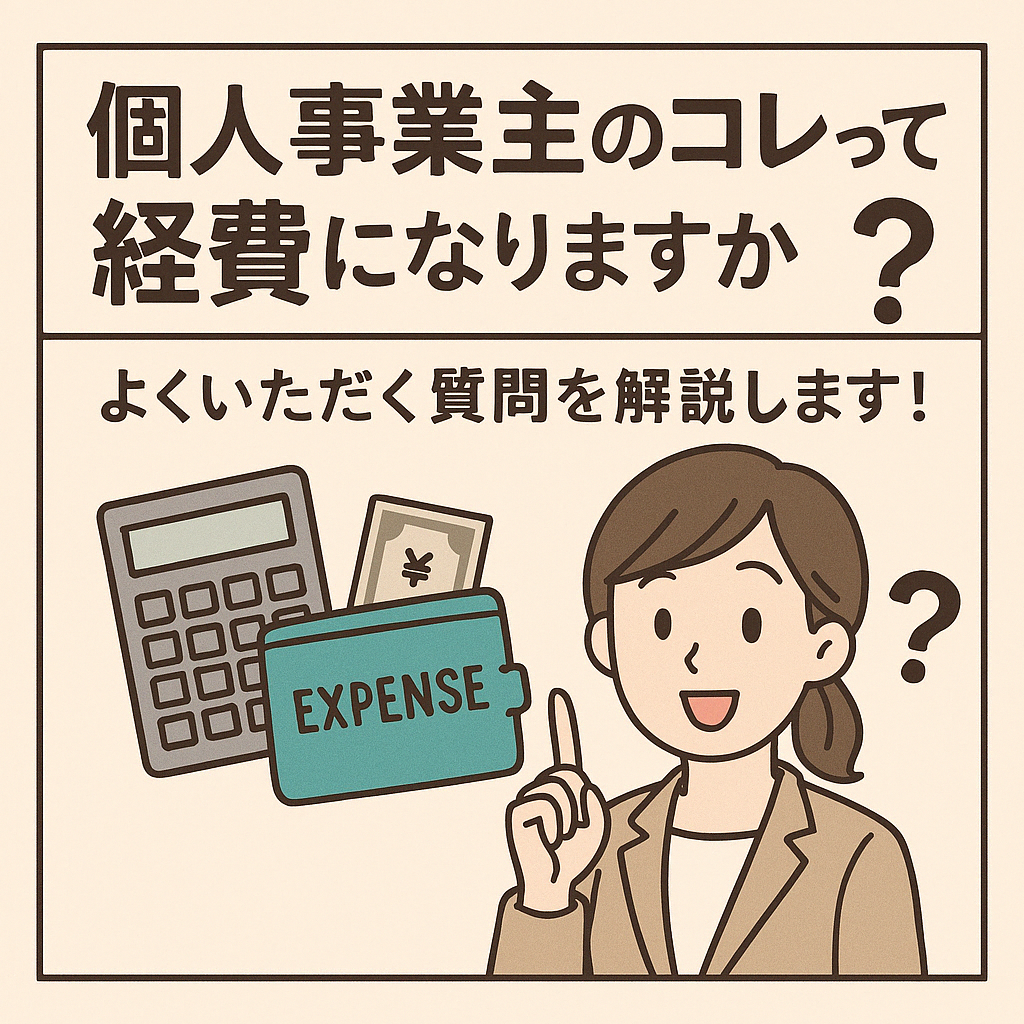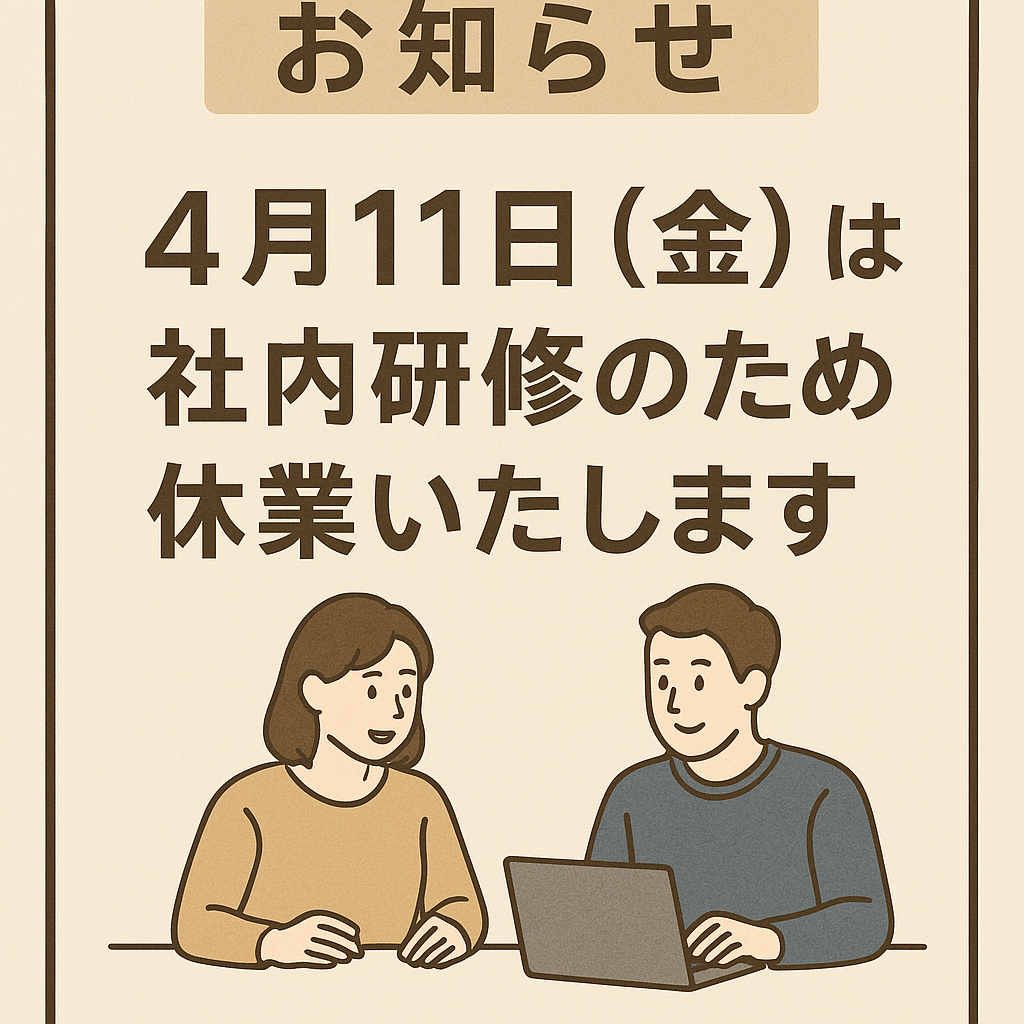こんにちは、FLOW会計の正木です!
クラウド会計ソフトを導入する企業が年々増えています。
でも、「マネーフォワードとfreee、どちらを選べばいいのかわからない…」というお声をよくいただきます。
どちらのソフトも日常的にサポートしている立場から、それぞれの良さや向いている企業タイプをお伝えできるのは私たちの強みです。
今回は、初めてクラウド会計を検討している方や、乗り換えを考えている方に向けて、マネーフォワードとfreeeの違いをわかりやすくご紹介します!
◆ そもそもクラウド会計ソフトってどう選ぶ?
選ぶときに意識したいのは、単なる「価格」や「機能数」だけではありません。
一番大切なのは、“自社の業務に合うかどうか“です。
チェックしたいポイントとしては、たとえばこんなところ:
- 操作がわかりやすいか
- 他のシステムやツールと連携できるか
- 導入後のサポート体制は十分か
- 拡張性や柔軟性があるか
このあたりを見ながら、次にそれぞれのソフトの特徴を見ていきましょう!
■ マネーフォワード クラウド会計の特徴
\ バックオフィス全体の効率化に強い! /
マネーフォワードは、会計にとどまらず、給与計算・勤怠管理・請求・経費精算などを一元管理できる「統合型クラウドツール」です。
社内の仕組みをまるごと整えたいときに、とても頼りになります。
◎ 特におすすめの企業タイプ
- 紙やExcelでの管理が中心だった企業
- 会計・人事・労務など、バックオフィス全体をまとめて効率化したい
- 管理部門が少人数で、業務を兼任している
- クラウド会計の導入が初めての企業
◎ 注目ポイント
- 会計・給与・経費などを1つのIDでまとめて操作可能
- プランによっては追加費用なしで多機能が利用可能
- 自動で帳簿やレポートが作成できるため、経営分析にも活用できる
- 導入時のサポートが手厚いので安心
■ freee会計の特徴
\ 自由な連携とカンタン操作が魅力! /
freeeは、業務の流れに沿った設計と、高い連携性・カスタマイズ性が特徴のクラウド会計ソフトです。
直感的な操作で、会計に詳しくない人でも使いやすい点が人気です。
◎ 特におすすめの企業タイプ
- Salesforceやkintone、SmartHRなど、他のクラウドツールを活用している
- 会計が苦手な担当者でも、流れにそって作業できるようにしたい
- スタートアップやフリーランスなど、スピード重視のビジネス
- 自社のやり方にあわせて、柔軟に運用したい企業
◎ 注目ポイント
- 見積→請求→入金→会計仕訳までを自動化できる業務フロー設計
- 外部ツールとの連携が豊富で、API連携によるカスタマイズも簡単
- スマホアプリが使いやすく、外出先からの経費入力や確認もスムーズ
- ノーコードで業務自動化(ワークフロー設定など)も可能
◆ 結局どっちを選べばいいの?
どちらを選ぶかは、「自社がどんな業務スタイルを大切にしているか」で決まってきます。
🔸 マネーフォワードがおすすめな方
- バックオフィス業務を一括でまとめたい
- 社内の業務フローを標準化したい・整備したい
- クラウド導入が初めてで、安心できるサポートが欲しい
- 機能は豊富だけど、使いやすさもしっかり重視したい
→ 業務基盤をしっかり整えたい中小企業や初導入の企業にぴったり!
🔸 freee会計がおすすめな方
- 他のITツールとの連携を重視している
- 会計に詳しくない人でも、直感的に操作できるソフトを使いたい
- 柔軟な業務フローに対応できるツールがほしい
- ノーコードやアプリを活用して、業務をどんどん自動化したい
→ スピード感のある会社や、IT活用が進んでいる企業に最適!
◆ まずはお気軽にご相談ください!
マネーフォワードとfreee、どちらもとても優れた会計ソフトですが、向き・不向きがあります。
私たちは両方のツールに精通しているので、中立的な立場から“本当に合うほう”をご提案することが可能です。
「うちにはどっちが合うんだろう?」
「まずは一度話を聞いてみたい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください!
クラウド会計の導入で、経理をもっとラクに、もっと強く。
一緒に、業務改善を進めていきましょう!