
こんにちは、FLOW会計の斉藤です。
インボイス制度の導入から1年が過ぎました。「ようやく慣れた…」とホッとしていませんか?しかし、本当の正念場はこれからです。
2026年10月、多くの小規模事業者の経営を直撃する「時限爆弾」、通称「2026年問題」が待ち構えています。
「知らなかった」では済まされない急激な負担増を避けるため、その正体と今すぐ取るべき対策を解説します。
■ あなたの事業を揺るがす2つの「激変」
2026年10月から、現在多くの事業者を支えている負担軽減措置が縮小・廃止されます。
- 経過措置の縮小(80%控除 → 50%控除へ)
現在、免税事業者からの仕入れでも、取引先は支払った消費税の「80%」を控除できます。つまり実質的な負担増は20%しかありませんでした。
しかし、2026年10月以降、この割合が「50%」にまで引き下げられます。
これにより、取引先は免税事業者との取引コストがグンと増えることになります。
免税事業者にとっては、値下げを要求されたり、最悪の場合、取引を打ち切られたりするリスクが現実的になるのです。
- 「2割特例」の完全廃止
インボイス登録に踏み切った元免税事業者の多くが活用しているであろう、まさに“救世主”ともいえる制度が「2割特例」。
これは、「売上にかかる消費税額の2割」だけを納税すればOKという、納税額も、事務負担も、大幅に軽減してくれる特例措置です。
この特例が、2026年9月末で完全に終了します!
(※個人事業主は2026年分の確定申告まで適用)
もし対策をしなければ、業種によっては納税額が数倍に跳ね上がる可能性があり、事業の資金繰りに深刻な影響を及ぼしかねません。
■ 生き残るための3つのアクション
1. 取引先と方針を協議する
特に免税事業者の方は、課税事業者になるのか、免税のまま価格で調整するのか、2026年10月以降の方針を主要な取引先と話し合いましょう。
事前の誠実な対話が、信頼関係と取引を維持する鍵です。
2. 最適な納税方法を決定する
2割特例終了後は「簡易課税」か「本則課税」を選択しなければなりません。事務負担が軽い「簡易課税」、設備投資など経費が多い場合に有利な「本則課税」。納税額で大きな差がつくことも。どちらが自社に有利か、シミュレーションしてみることが重要です。
- 簡易課税:業種ごとに定められた「みなし仕入率」で計算。実際の経費計算が不要で、事務負担が軽いのが特徴。
- 本則課税:売上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引いて計算。インボイスの集計・保存が必須で手間は増えますが、大きな設備投資などがある場合は有利になることも。
3. ITツールと補助金をフル活用する
増える事務負担は、デジタル化で乗り切りましょう!これからの時代、ITツール導入は不可欠です。 「でも、コストがかかる…」とためらう必要はありません。国は、事業者のデジタル化を支援する強力な補助金を用意しています。
- IT導入補助金(インボイス枠):クラウド会計ソフトやPC、タブレットの購入費用などを、最大8割という高い補助率で支援するものです。
- 小規模事業者持続化補助金:インボイス対応に限らず、販路開拓や生産性向上のための幅広い経費に利用できます。
補助金は、コストを抑えて未来への投資ができる絶好のチャンスです。
公募期間には限りがあります。今すぐ最新情報をチェックし、積極的に活用を検討してください。
■ まとめ
2026年10月は、小規模事業者にとって大きな転換点です。「まだ先」と先延ばしにせず、今日から準備を始めましょう。「取引先との対話」「納税方法シミュレーション」「ITツールと補助金の活用」。この3つの行動が、あなたの未来を守ります。
今すぐアクションを起こすことで、来るべき変化の波を乗りこなし、あなたの事業をさらに強く成長させることができるはずです。
不安な点があれば、一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。
未来のために、今日から一歩を踏み出しましょう!

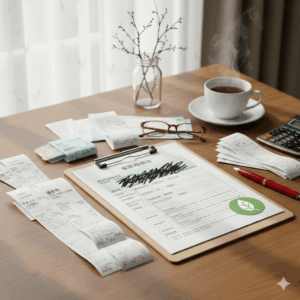
No comment yet, add your voice below!