
~相続税のトラブルを防ぐために今からできること~
相続や税務調査と聞くと、少し身構えてしまう方も多いのではないでしょうか。特に税務署が注目する項目の一つが「名義預金」です。
この記事では、名義預金がなぜ問題になるのか、そして将来の税務調査で指摘されないために、今からできる対策について分かりやすく解説します。
名義預金とは?
名義預金とは、口座の名義人と実際のお金の所有者が異なる預金を指します。
典型的な例は、親が子や孫名義で銀行口座を作り、自分の財産をそこに積み立てているケースです。
税務調査では、亡くなった方(被相続人)の財産だけでなく、家族全員の口座を過去10年分さかのぼって調査(場合によっては10年を超えて調査することも)します。その中で、家族名義の口座に不自然な多額入金が見つかると、税務署は
「実は亡くなった方の財産ではないか?」
と疑い、相続財産に含めようとします。
こうして名義預金は、相続税の課税対象となりやすいのです。
名義預金と生前贈与の違い
「親からもらったお金なのに、なぜ相続財産になるの?」と疑問を抱く方もいるでしょう。
これは、**「名義預金」と「生前贈与」**の成立要件が異なるためです。
生前贈与が成立するための条件
- 贈与する側が「あげる」という意思を示すこと
- 受け取る側が「もらう」という意思を示すこと
- 年間110万円を超える場合は贈与税の申告を行うこと
これらがそろって初めて「贈与」として認められます。
もし贈与税の申告がされていなかったり、子が実際にはそのお金を使えず親が管理していたりすると、
「贈与は成立していない」
と判断され、名義預金として相続財産に含められてしまいます。
税務署が名義預金を重視する理由
贈与税には通常6年の時効(※)があります。
しかし税務署は、贈与として課税できなくても、相続税としてなら課税可能なため、名義預金を厳しくチェックします。
つまり、過去にさかのぼって税金を徴収できる手段として、税務署が特に注目しているのです。
※もし、贈与税の申告を一切していない場合や、悪質な無申告・仮装隠蔽がある場合は、時効が7年に延びます。
相続税トラブルを防ぐための3つの対策
① 贈与の意思を記録に残す
お金を渡す際は贈与契約書を作成しましょう。
市販のひな形で十分有効です。日付や金額、双方の署名・押印を忘れずに。
② 受贈者自身が管理する
贈与されたお金は受贈者本人の口座に入金し、本人が管理・使用することが重要です。
親が通帳や印鑑を管理していると、名義預金とみなされる可能性が高くなります。
③ 贈与税を正しく申告する
年間110万円を超える贈与は必ず申告しましょう。
申告書自体が「贈与の事実」を証明する最も確実な証拠になります。
2024年からの新ルールに注意
2024年1月から、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されることになりました。
以前よりも広い期間が対象となるため、計画的な贈与が一層重要になっています。
まとめ
名義預金は税務調査で必ず確認される重要なポイントです。
最も大切なのは、「財産の所有者を明確にし、正しい申告を行うこと」
相続や贈与は複雑で、ケースによって最適な対策は異なります。
不安がある場合は、正しい申告と納税をするためにも、早めに税理士など専門家に相談することを強くお勧めします。
準備を前もって整えることで、大切な家族に余計な負担を残さず、安心して未来につなげることができます。

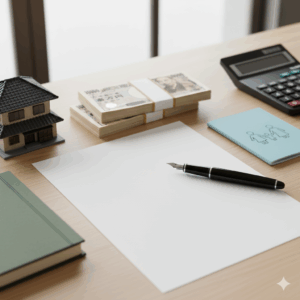

No comment yet, add your voice below!