
こんにちは!FLOW会計事務所の森です。
「相続税」という言葉を聞くと、難しそう、自分には関係ない、と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか? しかし、相続は突然やってくるものであり、適切な準備をしていないと、大切な財産を円滑に次世代に引き継げない可能性があります。この記事では、相続税の基本的な仕組みから、今からできる賢い対策まで、分かりやすく解説します!
■ 相続税の基本を知ろう
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときに課される税金です。国税庁のデータによると、実は全国の亡くなられた方の「約10人に1人」が相続税の課税対象となっています。決して他人事ではない、身近な税金と言えるでしょう。
■ 基礎控除額とは?
相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、この金額内であれば相続税はかかりません。 基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。例えば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人など)の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。この金額以下であれば、原則として相続税の申告も不要です。
■ 相続税がかかる財産・かからない財産
財産には、相続税の対象になるものとならないものがあります。
<課税対象となる財産>
現金、預貯金、不動産、株式、有価証券、生命保険金(非課税枠を超える部分)、死亡退職金(非課税枠を超える部分)などです。
<非課税となる財産>
墓石、墓地、仏壇、公益を目的とする事業に使われるもの、そして一定の非課税枠内の生命保険金や死亡退職金などです。 相続財産を正確に把握することが、適切な相続税計算の第一歩です。特に不動産や株式の評価は専門的な知識が必要な場合もあります。
■ 今からできる賢い相続税対策
相続税対策は、早くから始めるほど選択肢が広がり、より効果的な準備ができます。
1. 生前贈与を上手に活用しよう
財産を生前に次世代へ引き継ぐ「生前贈与」は、有効な相続税対策の一つです。 年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。この非課税枠は、令和6年(2024年)から、相続時精算課税制度を選択した場合でも利用できるようになり、利便性が向上しました。ただし、亡くなる前7年以内の贈与は、原則として相続財産に持ち戻されて(加算されて)相続税の対象となるため注意が必要です。ただし、孫等一定の親族等への贈与は、この7年加算の対象外となる場合もあります。
2. 教育資金や生活費の援助は非課税
「必要な時に必要な額を親族に与える」という目的であれば、教育資金や生活資金の援助は、贈与税の対象になりません。例えば、孫の医学部の入学金2,000万円を祖父が出しても非課税となることがあります。これは民法上の扶養義務に基づくもので、特別な手続きが不要な場合もあります。
3. 生命保険の非課税枠を活用
生命保険金には、法定相続人の数に応じた非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」が非課税となる金額です。例えば、法定相続人が2人であれば1,000万円までが非課税になります。預貯金で持っているよりも、生命保険に加入することで、この非課税枠を有効活用し、相続税を抑えることが可能です。
4. 二次相続を見据えた計画
「二次相続」とは、両親のうち片方が亡くなり、その後にもう片方も亡くなる際の相続を指します。二次相続では、配偶者の税額軽減が適用されず、基礎控除額も少なくなることなどから、一次相続よりも相続税の負担が重くなる傾向があります。そのため、一次相続の段階から、二次相続を見越した財産配分を検討することが非常に重要です。
■ まとめ
相続税対策は複雑で、ご家庭の状況や財産の状況によって多岐にわたります。インターネットの情報だけで判断が難しい場合も少なくありません。早めの準備と、税理士などの専門家へのご相談が、安心して財産を次世代へ引き継ぐための最も確実な方法です。当会計事務所でも、お客様に寄り添い、最適な相続対策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます!

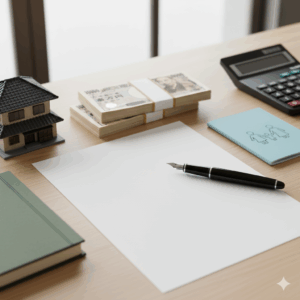
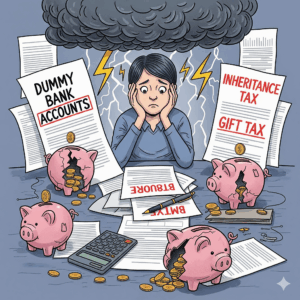
No comment yet, add your voice below!