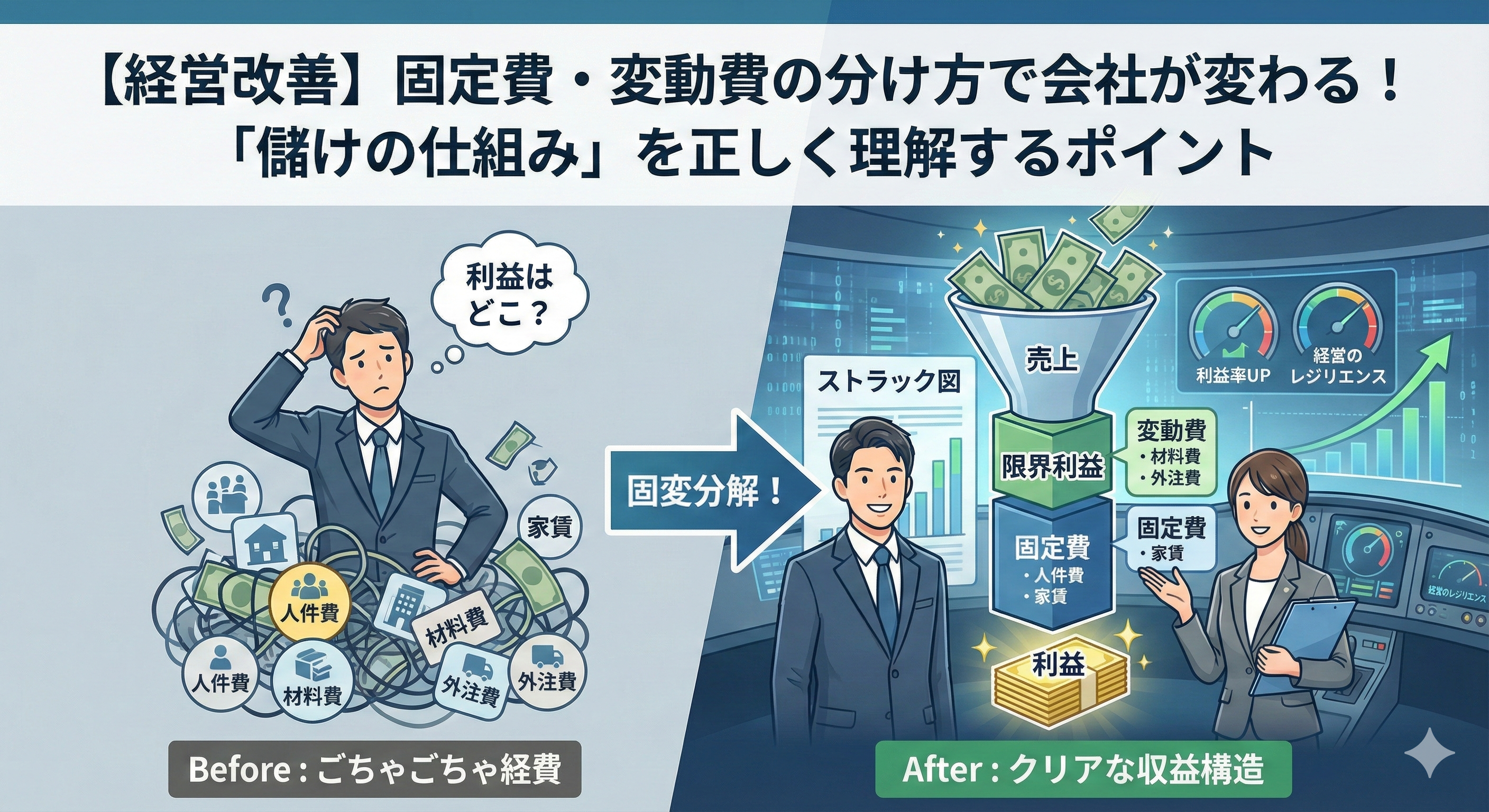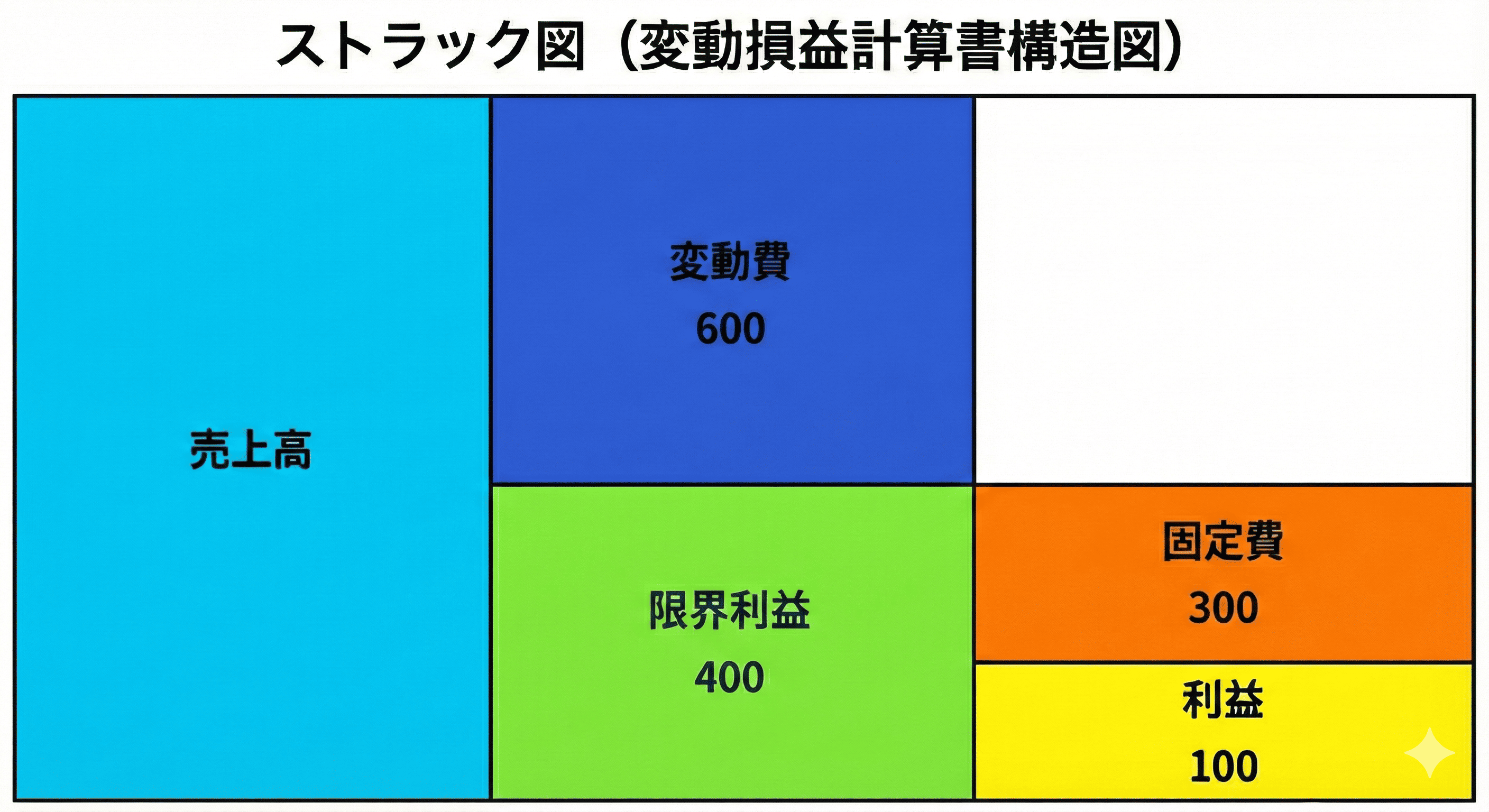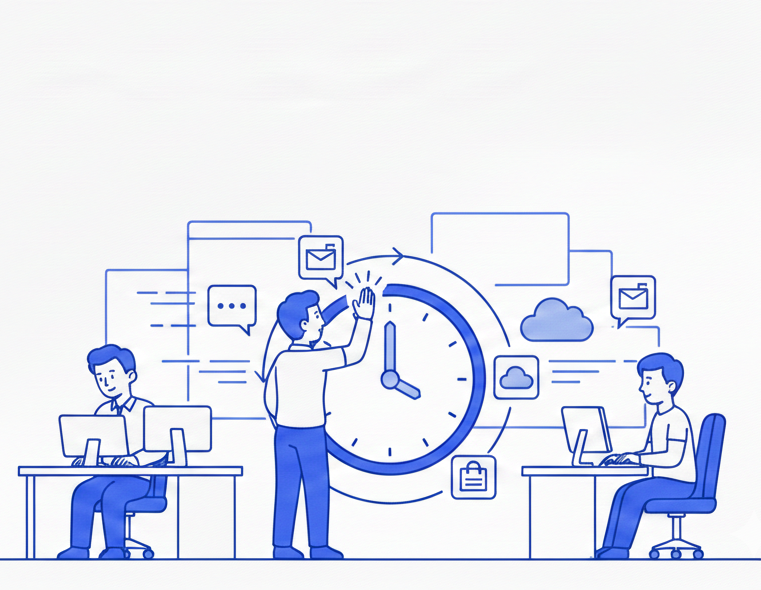こんにちは!つくば市にある税理士法人FLOW会計事務所の堀です。
12月に入り、寒さが一段と厳しくなってきましたね。この時期は風邪やインフルエンザも流行しやすく、体調管理が難しい季節です。
さて、年末といえば大掃除ですが、お部屋の掃除と一緒にぜひやっていただきたいのが「医療費の領収書(レシート)の整理」です。
「うちはそんなに病院に行っていないから関係ない」 そう思っている方こそ、実はもったいないことをしているかもしれません!
今回は、意外と誤解が多い「医療費控除(いりょうひこうじょ)」と、最近よく耳にする「セルフメディケーション税制」のポイントについて、分かりやすく解説します。
医療費控除は「10万円」超えたら?だけではありません
医療費控除とは、簡単に言うと「1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすれば税金が安くなる(戻ってくる)」という制度です。
よく「医療費は10万円を超えないとダメ」と耳にしますが、これには例外があります。
その年の総所得金額等が200万円以上の方: 10万円を超えた分が対象
その年の総所得金額等が200万円未満の方: 総所得金額等の5%を超えた分が対象
つまり、所得が少なめの方や、パート・アルバイトの方であれば、医療費が10万円に行かなくても控除を受けられる可能性があるのです。あきらめずに計算してみる価値は十分にあります。
そのレシート、捨てないで!対象になるもの・ならないもの
医療費控除の計算をする時、一番迷うのが「これは医療費に入るの?」という点です。 基本的な考え方は、「治療のためならOK、予防や美容のためならNG」です。
【〇 対象になるものの例】
・医師、歯科医師による診療・治療代
・治療のための医薬品代(医師の処方箋がなくても、風邪薬や頭痛薬などの一般的な市販薬も対象です)
・通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
・妊娠中の定期検診、出産費用
・子どもの歯列矯正(※医学的に必要と認められる場合)
【× 対象にならないものの例】
・健康診断、人間ドックの費用(※結果、病気が見つかり治療した場合は対象)
・予防接種(インフルエンザワクチンなど)
・美容整形、美容目的の歯列矯正
・マイカー通院のガソリン代、駐車場代
特に見落としがちなのが、通院のための「電車・バス代」です。領収書が出ませんが、日付と経路、金額をメモしておけば認められますので、必ず記録しておきましょう。
病院にはあまり行かないけれど…「セルフメディケーション税制」とは?
「病院にはほとんど行かなかったけれど、ドラッグストアで高めの風邪薬や胃腸薬をたくさん買った」 そんな方のために、2017年から始まったのが「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。
これは、きちんと健康診断など(※)を受けている人が、対象となる「特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)」を年間で1万2千円を超えて購入した場合に利用できる制度です。 (※会社の健康診断、人間ドック、インフルエンザの予防接種などが該当します)
通常の医療費控除(10万円の壁)よりも、ハードルがかなり低いのが特徴です。
対象となる薬のパッケージには、識別マークが付いていたり、レシートの商品名の横に「★」や「セ」といった印字がされていたりします。ご自宅の薬箱やレシートを確認してみてください。
重要!「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」、どっちがお得?
ここが最も重要なポイントです。 この2つの制度は、「どちらか片方しか選べません(併用不可)」。
「病院代で5万円、対象の市販薬で3万円使ったから、両方使おう!」ということはできないのです。 では、どちらを選べばよいのでしょうか?
ざっくりとした判断基準は以下の通りです。
「通常の医療費控除」を選んだ方が良い人: ・入院や手術などで、病院に支払った金額が大きい人
・家族が多く、全員の通院費を合わせると10万円を超えそうな人
「セルフメディケーション税制」を選んだ方が良い人:
・病院にはほとんど行かないが、対象となる高機能な市販薬を年間1万2千円以上買った人
(かつ、会社の健康診断などをきちんと受けている人)
どちらが得かは、実際に集計して計算してみないと分かりません。少し面倒ですが、両方のパターンで計算してみて、控除額が大きくなる方を選択するのが賢い方法です。
【共通のコツ】家族全員分をまとめて申告しましょう
どちらの制度を選ぶにしても、「生計を一(いつ)にする家族」の分をまとめて申告できる点は同じです。
単身赴任のお父さんや、下宿している大学生のお子さんの分も、お財布(生活費)が一緒であれば合算可能です。一人ひとりでは大した金額にならなくても、家族全員分を合わせれば対象になるケースはよくあります。
また、家族の中で誰が申告するか選ぶことができますが、一般的には「一番所得税率が高い(お給料が高い)人」が申告したほうが、戻ってくる税金が多くなり有利です。
まとめ:今のうちに領収書を集めておきましょう
年が明けてから「あの領収書どこだっけ?」と慌てないように、この年末に一度、家中の医療費や薬局のレシートを集めてみてください。
家族全員分の領収書を集める
→「病院の領収書」と「ドラッグストアのレシート」に大まかに分ける
→ドラッグストアのレシートは、セルフメディケーション対象商品かチェックする
もし、計算や「どちらの制度がお得か」の判断に迷うことがあれば、私たちFLOW会計事務所にお気軽にご相談ください。 早めの準備で、安心してお正月を迎えましょう!