
皆様、こんにちは。FLOW会計事務所の正木です。
毎月の給与明細で気になるのが、最終的な「手取り額」です。給与から差し引かれている「控除額」の仕組みを知ることは、ご自身の資産管理の第一歩です。
今回は、この控除額に含まれる税金と社会保険料の基本的なルールを、専門家の視点から分かりやすく簡潔に解説します。
1. 給与計算の基本:総支給額と控除額の関係
給与計算は以下の通りです。
【(総支給額) – (控除額) = (手取り額)】
控除額は、法律で引くことが義務付けられており、大きく「税金」と「社会保険料」の2つに分けられます。
2. 給与から引かれる「税金」の仕組み
給与から控除される主な税金は、所得税(国税)と住民税(地方税)です。
2-1. 所得税:毎月「仮払い」し、年末に「清算」
所得税は、1年間の収入に対してかかる税金です。
- 毎月の処理: 年間の収入を予測し、「仮払い」として概算で毎月差し引かれています。
- 年末調整の役割: 家族構成や保険料の支払いといった個人的な事情は、月々の仮払いに反映されていません。
そこで、1年の終わりに正しい税額を計算し直し、仮払いした合計額との過不足を清算します。- 払いすぎの場合: 還付金(お金が戻る)
- 不足の場合: 追加徴収
2-2. 住民税:「去年の収入」で決まる確定額
住民税は、所得税と異なり、「去年の収入」に基づいて税額が確定します。
- 納め方: 確定した年間税額を、通常6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月お給料から引かれます。
- ポイント: 金額は確定済みのため、年末調整の対象にはなりません。
3. 手取りを増やすカギ:年末調整での申告
年末調整で税金が安くなるのは、あなたが支払った特定の費用(保険料など)を申告することで、税金がかかる対象の収入が減る(控除される)ためです。
- 申告が必要なもの: 生命保険料や地震保険料などの控除は、会社から配られる申告書に漏れなく記入して提出することで適用されます。
- 重要性: この申告を正しく行うことが、本来受けられる控除を適用し、納める税金を適正化するために非常に大切です。
4. もう一つの控除:「社会保険料」の基礎
社会保険料は、病気、老後、失業など、「もしも」の事態に備えるための費用です。
- 主な種類: 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(40歳以上)、雇用保険料など。
- 決まり方: あなたの給与額に基づいた「ランク」に応じて保険料が計算されます。
まとめ
給与計算は、労働基準法、社会保険、税金など、様々な法令や制度が複雑に絡み合って成立しています。ご自身の給与明細を理解し、年末調整を正確に行うことは、ご自身が本来受けるべき控除をしっかりと適用するために欠かせません。申告書への記入や計算方法に不安がある際には、ぜひFLOW会計事務所にご相談ください!

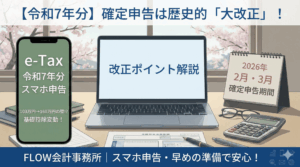

No comment yet, add your voice below!