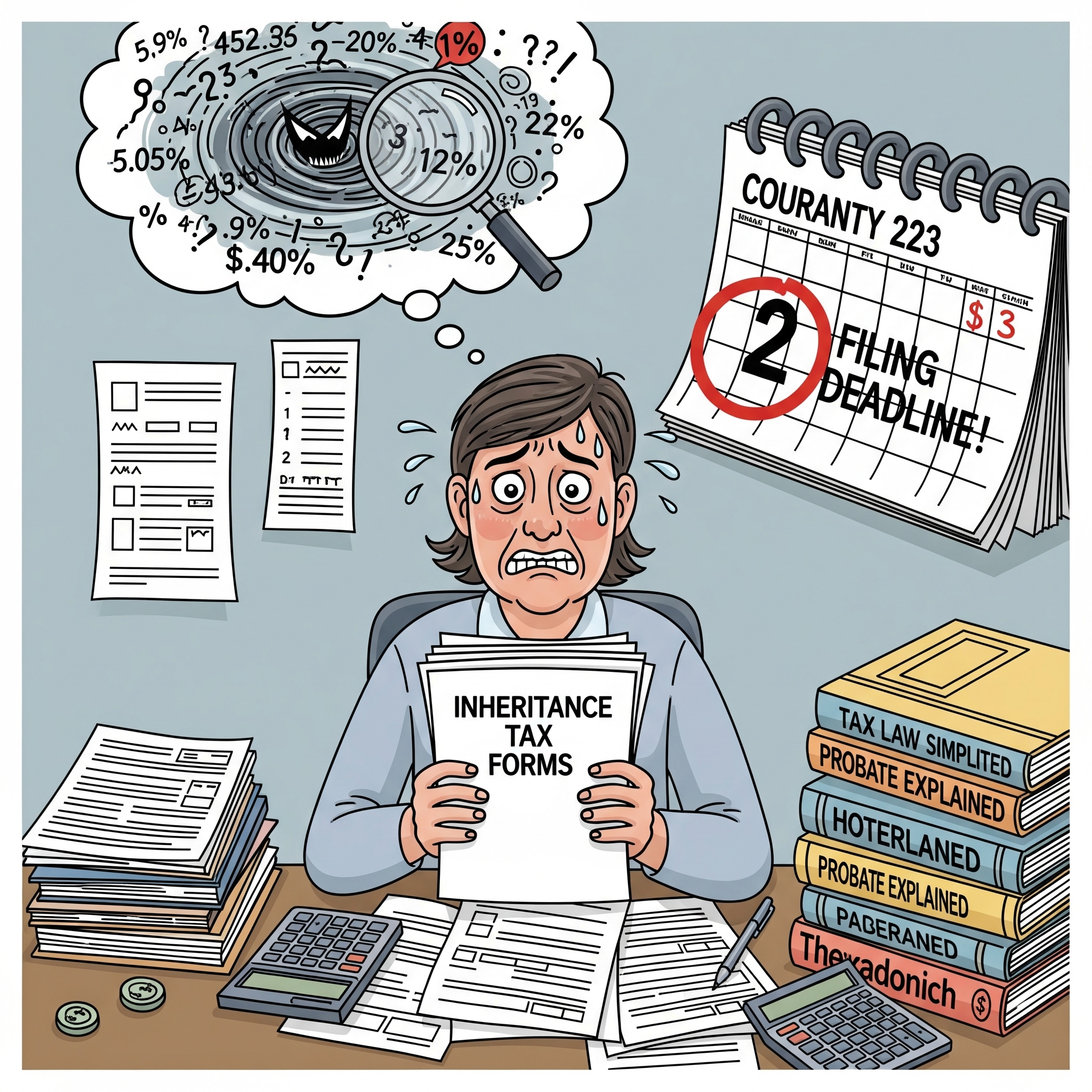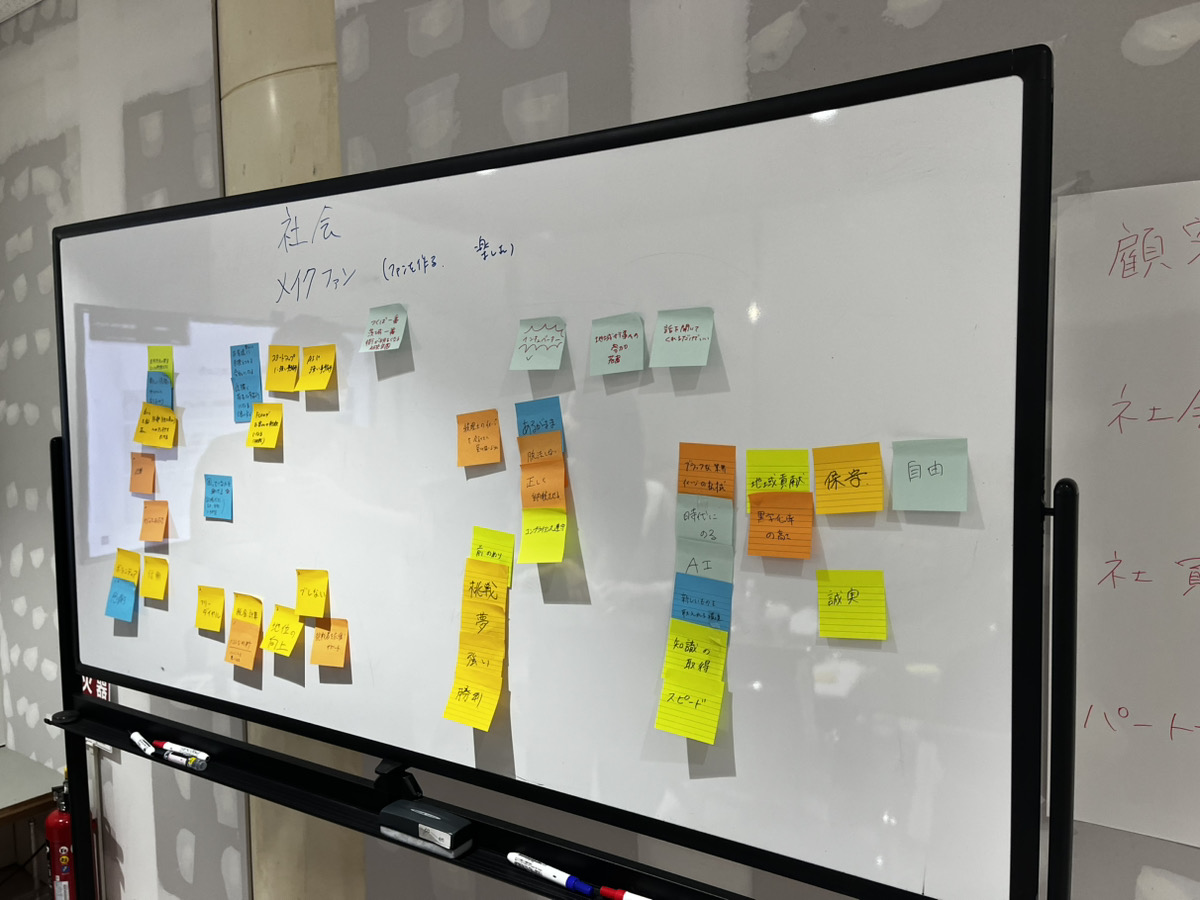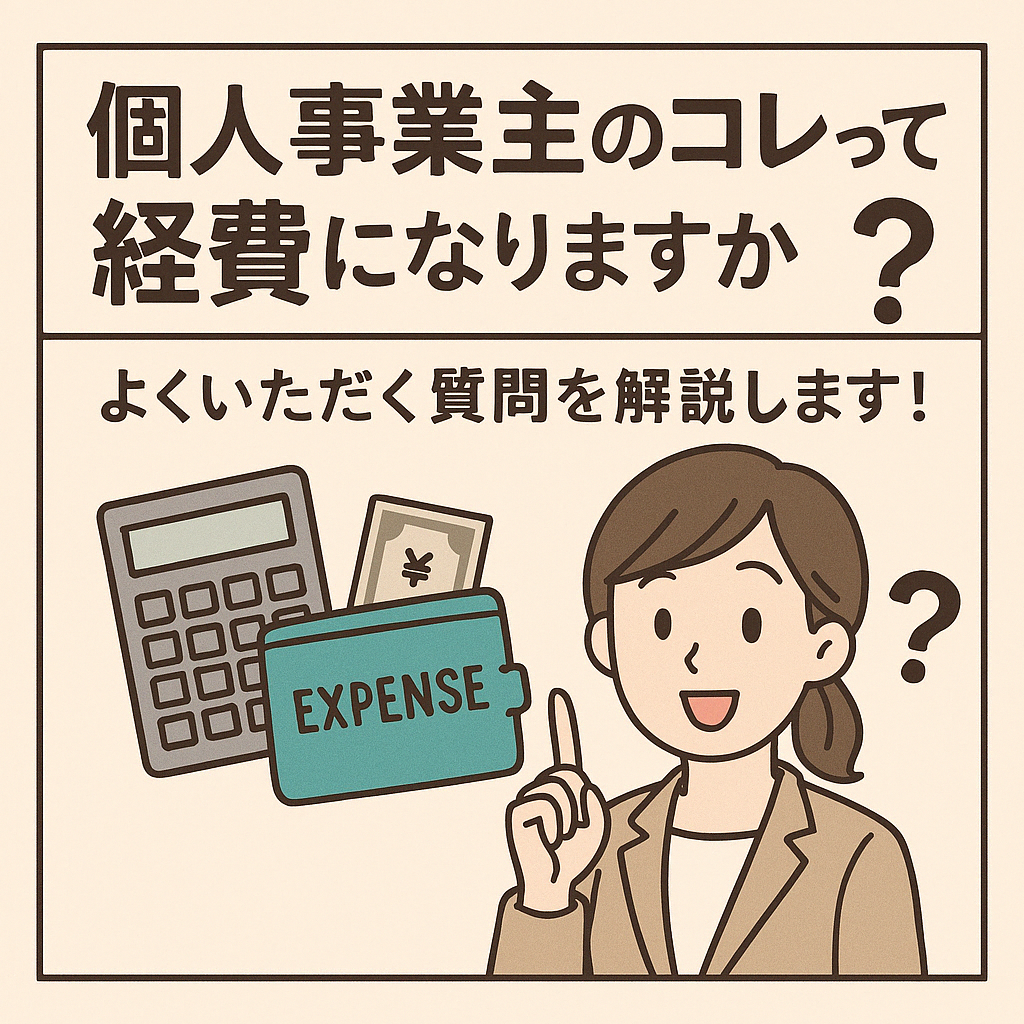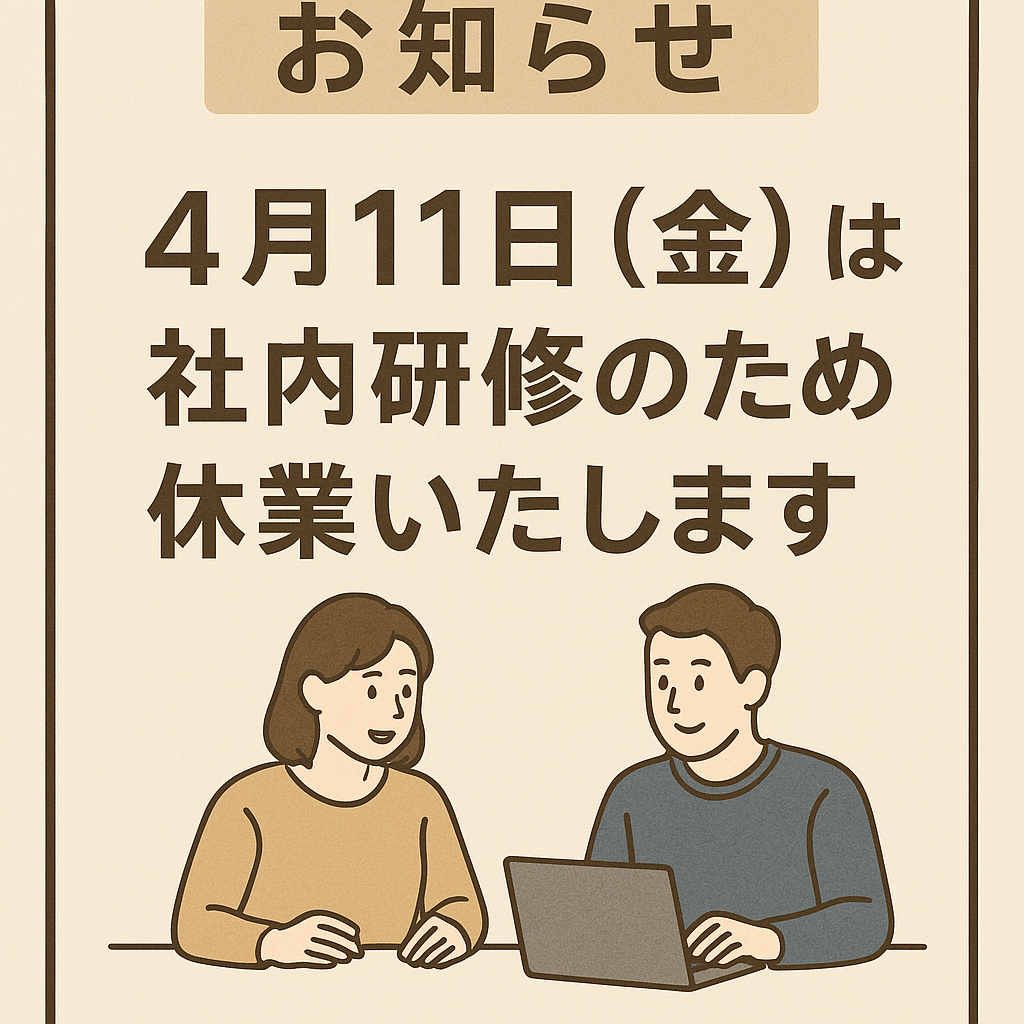こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所の庄司です。
突然ですが、消費税やインボイス制度について、「難しくてよくわからない…」と感じていませんか?特に2026年10月には、制度に大きな変更が予定されております。
「1年後だからまだ先」と思うかもしれませんが、早めに知っておくに越したことはありません。今のうちから少しずつ準備をしておきましょう。
この記事では、インボイス制度の基本から、2026年10月以降の変更点、事業への影響、そして今からできる対策を分かりやすく解説します。
1. 消費税の基本をおさらい
消費税は、消費者が負担し、事業者が国に納める税金です。
基本的な計算方法は、お客様から受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引く「本則課税」です。ただし、土地の売買や利子、補助金などは消費税がかからない「非課税取引」となります。
2. 課税事業者になる条件
消費税を納める義務がある「課税事業者」は、基本的には以下のいずれかに当てはまる事業者です。
- 2年前の課税売上高が1,000万円を超えている
- インボイス発行事業者として登録した
本来、売上が1,000万円以下で免税事業者であっても、インボイス登録をすると、自動的に課税事業者となり、消費税を納める義務が発生します。
3. 【重要】2026年10月からの大きな変更点
現在運用中のインボイス制度ですが、2026年10月以降に特に重要な2つの変更が予定されています。
① 免税事業者からの仕入れに関する控除率の変更
現在、免税事業者から仕入れを行った場合、消費税相当額の80%を「経過措置」として控除できます。しかし、2026年10月からはこの控除割合が50%に変更されます。
この変更は、免税事業者と取引のある課税事業者にとって、納税額の増加を意味します。その結果、課税事業者が負担増を避けるために、免税事業者への支払額を減額したり、取引を停止したりする可能性が懸念されています。
② 2割特例の廃止
インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者に転換した方が利用できる「2割特例」が、2026年9月末で廃止される予定です。
この「2割特例」は、売上にかかる消費税額の2割だけを納税すればよいという、事務負担の少ない制度です。廃止されると、多くの事業者は「簡易課税」または「本則課税」のどちらかで消費税を計算・申告しなければならなくなります。これにより、納税額が増え、事務作業の負担も重くなる可能性があります。
4. 消費税の計算方法を再確認
2割特例廃止後、主に以下の2つの計算方法が中心になります。
① 本則課税(原則課税)
「受け取った消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて納税額を計算する、原則的な方法です。全ての取引について消費税額を細かく集計する必要があり、事務負担は大きくなります。
② 簡易課税制度
2年前の売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。「受け取った消費税額」に、業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算するため、個別に集計する手間が省けます。適用には事前の届け出が必要です。
どちらが有利かは事業内容や状況によって異なるため、ご自身のケースでシミュレーションを行うことが重要です。
5. 消費税負担を抑えるためのポイント
来るべき制度変更に備えて下記の点を確認しておきましょう。
① インボイス登録の要否を検討
取引先が一般消費者(BtoC)中心の場合など、インボイスを求められないケースでは、あえてインボイス登録をせず、免税事業者のままでいる選択肢も有効です。
② 法人設立時の資本金
法人を設立する際、資本金を1,000万円未満に設定することで、設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除される制度を活用できます。
③ 納税資金の準備
消費税は、たとえ赤字であっても納税義務が発生する場合があります。納税資金は、運転資金とは別に、日頃から計画的にプールしておくことが非常に重要です。
まとめ
2026年10月以降、インボイス制度の変更は、特に個人事業主やフリーランスの方々の消費税に関する負担を大きく変える可能性があります。
ご自身の事業に合った最適な対策を見つけるためには、専門家への相談が不可欠です。消費税の計算や節税対策は、事業内容や売上規模によって最適な選択肢が異なりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!