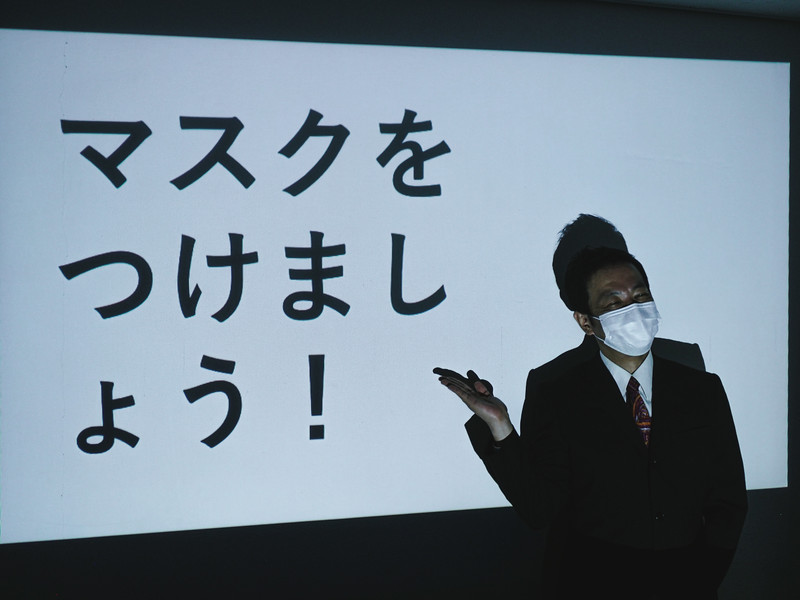【数字でみるアフターコロナ(新設法人編)】
今回は、ビフォアーコロナとアフターコロナの法人設立数について調べてみました!
「これだけ不景気なんだからビジネスはじめるやつなんて、いるわけないだろ!」
そんな声が聞こえてきそうですが、実はそんなことはなさそうなんです。
さっそく、数字を見ていきましょう!
【2020年(2019年)】
茨城県内で新しく法人が設立された数です。
1月 156件(153件)前年比+3件
2月 115件(113件)前年比+2件
3月 182件(162件)前年比+20件
4月 179件(176件)前年比△3件
5月 101件(169件)前年比△68件
6月 140件(148件)前年比△8件
7月 167件(172件)前年比△5件
8月 151件(135件)前年比+16件
9月 136件(142件)前年比△6件
2020年1~9月合計1327件(2019年1~9月合計1370件)
2020年1~9月の法人設立数は2019年1~9月より「43件」減でした。
月別に見ていくと2020年5月期は△68件の大幅減でしたが、コロナが少し落ち着いた8月期は+16件と盛り返しています。
割合でみても前年比3%程度の減なので、2019年より減るには減っているけれども、コロナの影響を受けているのかっていうと、正直、微妙な判定にはなると思います。
直近のデータになるので業種別に拾うことまではできなかったのですが、ウィズコロナとしてこのピンチをチャンスと捉えて新しいビジネスにトライしようとしている人が一定数いることがこの数字からもわかりますね。
ちなみに東京はどうだったのかも気になったので調べてみました。
1月 3648件(3342件)前年比+306件
2月 3137件(3133件)前年日△4件
3月 3931件(3446件)前年比+485件
4月 3031件(3733件)前年比△702件
5月 2493件(3445件)前年比△952件
6月 3069件(3331件)前年比△262件
7月 3446件(3688件)前年比△242件
8月 3149件(3243件)前年比△94件
9月 3338件(3173件)前年比+165件
2020年1~9月合計29242件(2019年1~9月合計30534件)
2020年1~9月の法人設立数は2019年1~9月より「1292件」減でした。
すごい減ったようにも感じますが前年比4%減程度なので、茨城も東京も似たような推移になっていました。
今回の数字からも、コロナ禍を新しいことへのチャレンジや業種転換のチャンスと捉えているビジネスマンが多くいることがわかりました。
変化をし続けることはビジネスの永遠のテーマですね。
あの「任天堂」も最初は花札の製造メーカーであったことはご存知でしょうか?
1889年に製造を開始し、カードゲームが衰退する1960年代には企業存続の窮地に立たされました。
そこでアナログゲームからデジタルゲームに転換し、1983年には家庭用ゲーム機「ファミリーコンピューター」をリリースします。
その後の活躍はみんな知っていますよね!
お隣の韓国では、自動車メーカーの「ヒュンダイ」が「Uber」と提携してエアタクシーという巨大なヘリのような移動機を現在進行形で開発していたりします。
都心部の空を旅客機型の大きなヘリが飛ぶなんて全く想像もつきませんが、人が発想しないことに大きなビジネスチャンスがあることは間違いありません。
コロナ禍を機会にどんなビジネスサービスが誕生するのか注目していきましょう!