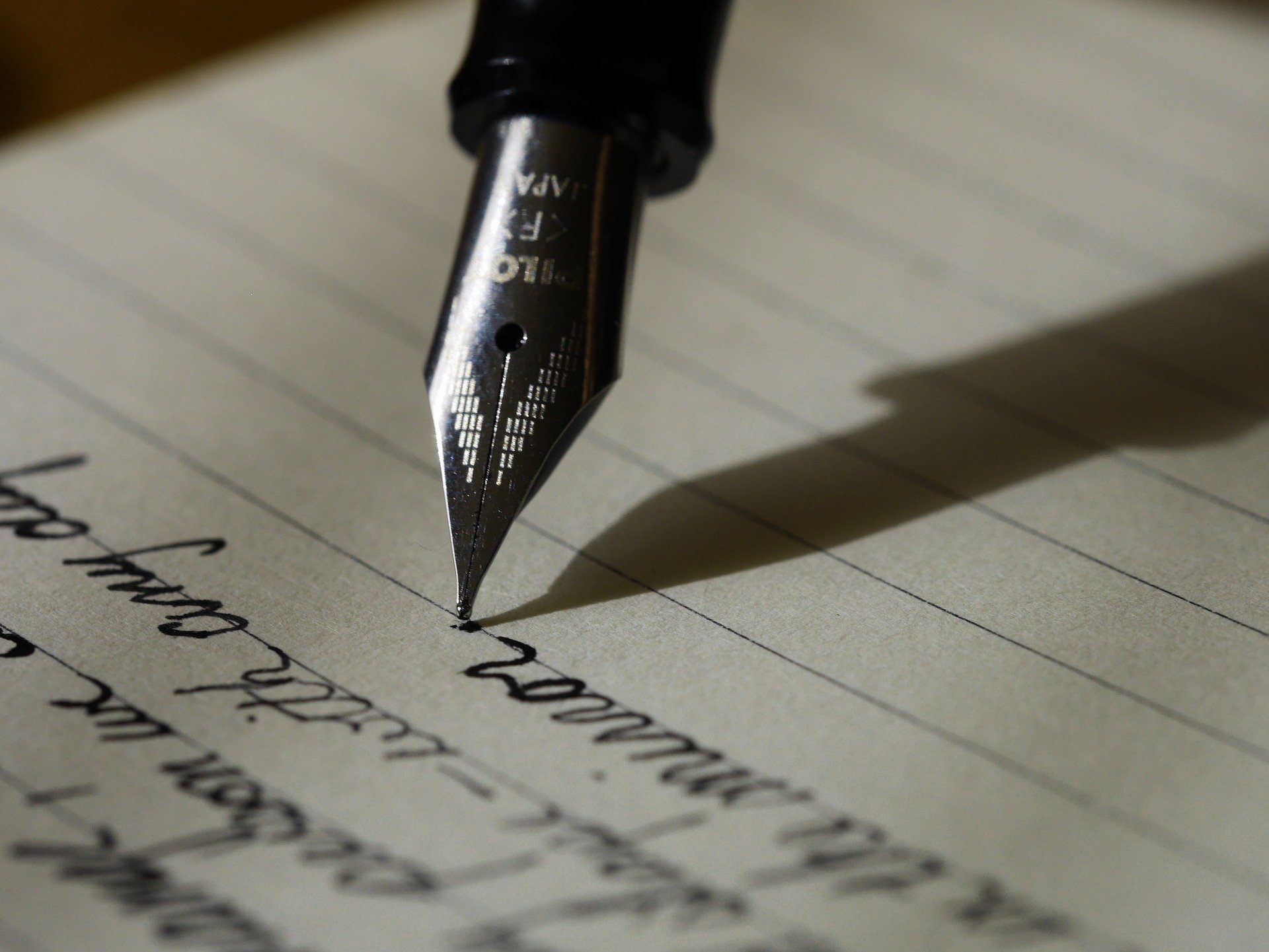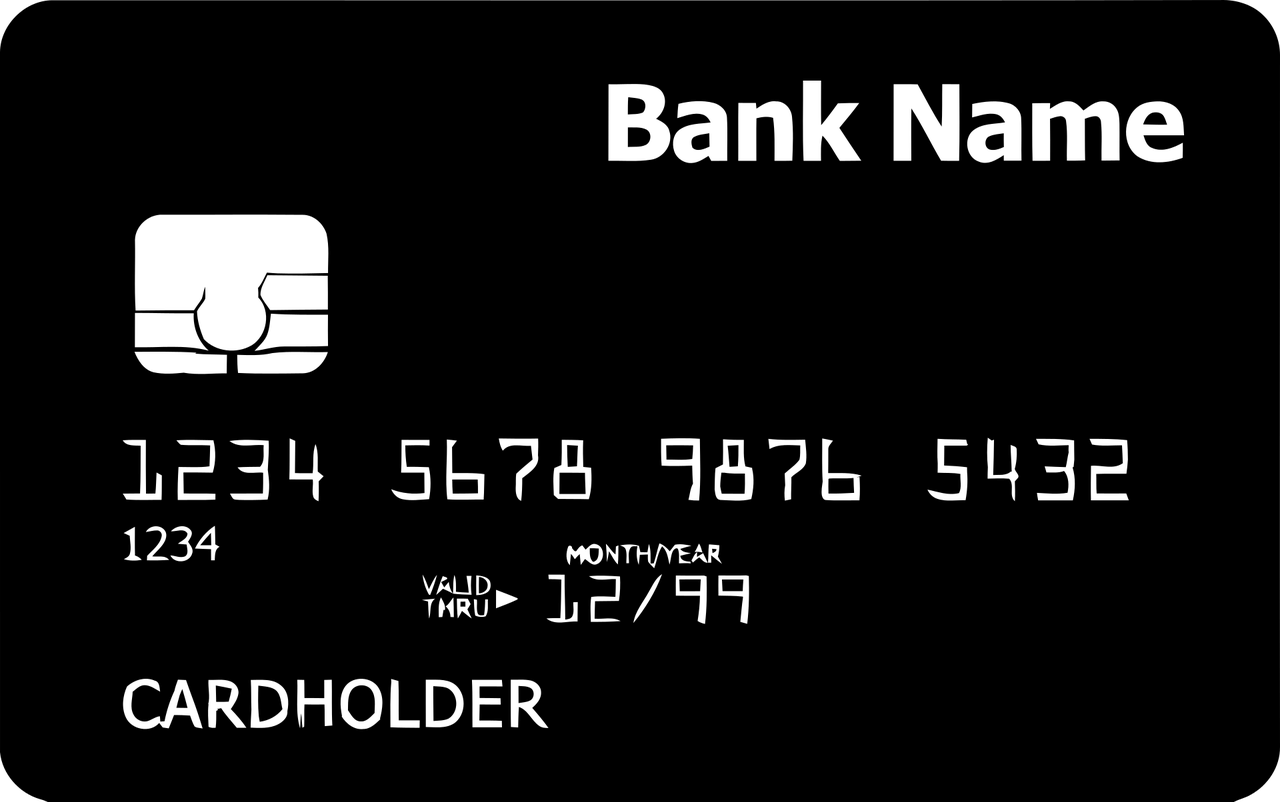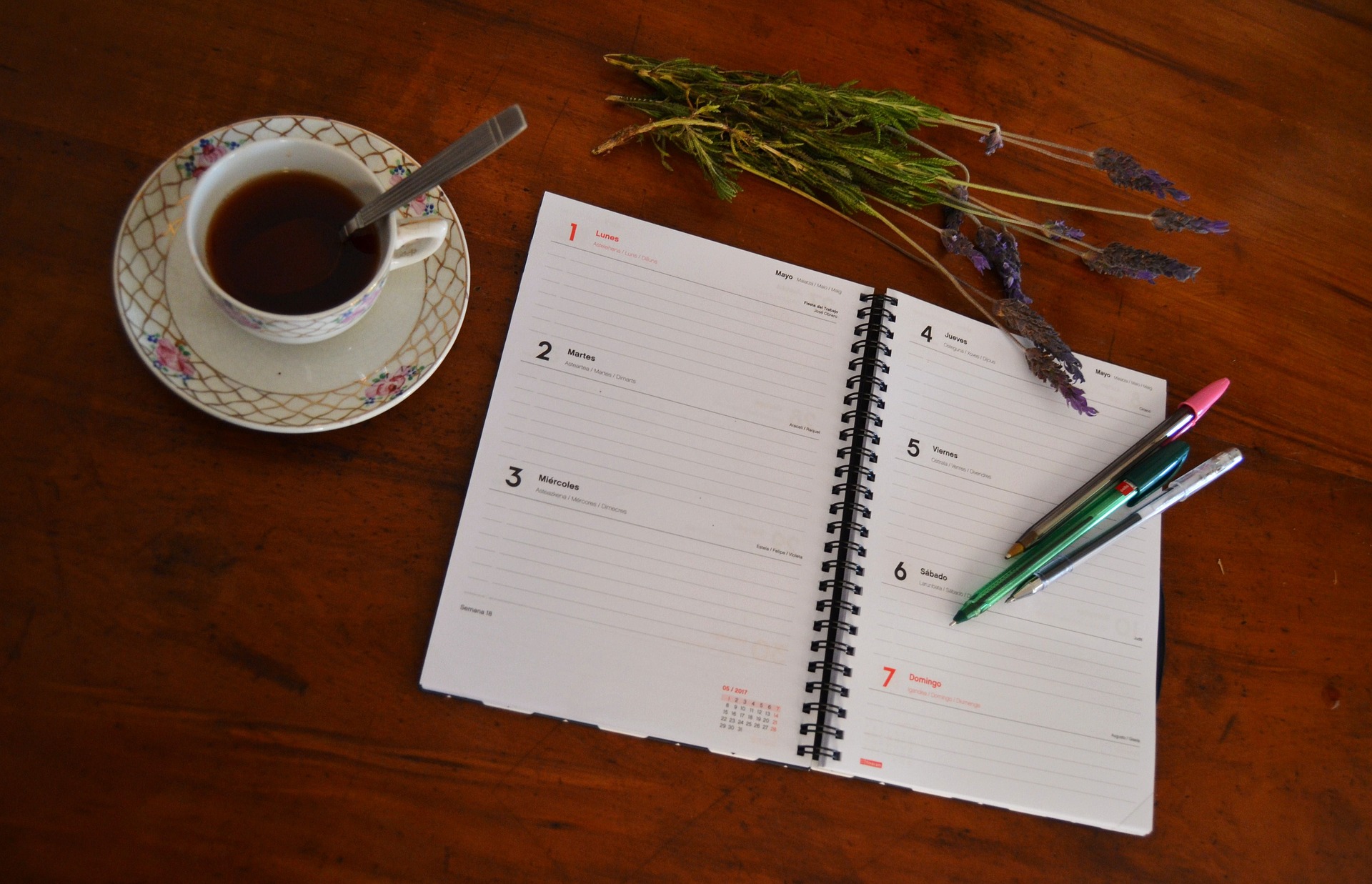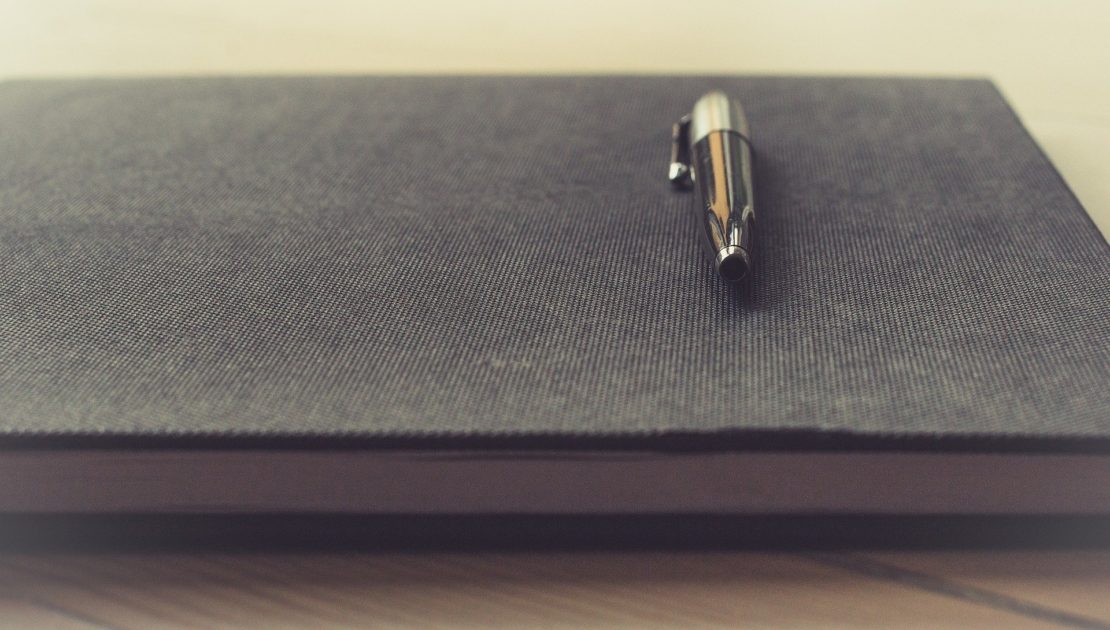【[相続税]配偶者の税額軽減と2次相続】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、配偶者の税額軽減と2次相続のハナシ。
配偶者の税額軽減と2次相続はセットで考える必要があります。
まずは「配偶者の税額軽減」って何なんでしょう?
◇配偶者の税額軽減とは
被相続人(亡くなった方)の配偶者を対象とする税の特典になります。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分
①と②、いずれか大きい金額までは相続税を無税にするという特典です。
簡単な例で考えてみましょう。
例)ケース1
被相続人(亡くなった方):Aさん
遺産総額:2億円
相続人:妻Bさん、子Cさん
配偶者の法定相続分:1/2
この場合、法定相続分によれば妻Bが相続する財産は1億円になります。
①1億6千万円>②法定相続分1億円→妻Bさんは1億6千万円まで無税
例)ケース2
被相続人(亡くなった方):Aさん
遺産総額:4億円
相続人:妻Bさん、子Cさん
配偶者の法定相続分:1/2
この場合、法定相続分によれば妻Bが相続する財産は2億円になります。
①1億6千万円<②法定相続分2億円→妻Bさんは2億円まで無税
分割協議により配偶者が法定相続分を超えて相続をし、かつ、配偶者の遺産相続額が1億6千万円を超えていなければ、被相続人の配偶者には相続税がかからないという制度になっています。
これは大きいですよね。
でも、これにはトラップがあるんです。そう、それはタイトルにも挙げている2次相続ですね。
配偶者の税額軽減を利用してたっぷり相続財産を受け取ったとします。
そして、その配偶者が亡くなったとしましょう。そうすると、配偶者の財産は、子らに相続されます。
しかし、子らに配偶者の税額軽減のような大きな特典はないため、ここ(いわゆる2次相続)でドカッと相続税がかかることになります。
また、2次相続では相続人の数が減っているケースがほとんどのため、基礎控除額も減ります。
先の例でいうと、妻Bさんの相続時の相続人は子Cさんのみとなります。
Aさんの相続時の相続人は2名(妻B、子C):基礎控除4200万円(3000万円+600万円×相続人2名)
妻Bさんの相続時の相続人は1名(子C):基礎控除3600万円(3000万円+600万円×相続人1名)
基礎控除額に600万円の差が生じてきます。
以上からも1次相続(Aさんの相続)の配偶者の税額軽減は、2次相続(妻Bさんの相続)まで踏まえて金額を決定する必要があります。
◇配偶者の税額軽減は2次相続まで考えよう
それではどのように財産を振り分ければ良いのでしょうか?
ポイントは2つです。
①配偶者が「これからの生活に必要な金額」を相続する
②①以外の財産は子供が相続する
「これからの生活に必要な資金」はあくまで想定になります。
「月の生活費○○円×12か月×(平均寿命△現在の年齢)」といったおおよその想定にはなります。
また、施設に入居される可能性がある場合にはそういった入居費用も考慮して決定した方が良いでしょう。
・配偶者→子への住宅資金の非課税贈与(最大1200万円)
・配偶者→孫への教育資金の非課税贈与(最大1500万円)
上記のような制度を利用すれば非課税で贈与することも可能ですので、配偶者の税額軽減の範囲の中で配偶者へ財産を寄せれば1次相続の相続税も節税することはできます。
以上、ポイント2つを挙げさせていただきましたが、1次相続の遺産総額の金額や内容によっては該当しないケースもありますので、ご注意を。
2次相続まで踏まえて1次相続の検討をしないと何百万円~何千万円の余計な相続税を払わなければならなくなる可能性もありますので、事前に専門家に相談することをオススメします。
税理士法人FLOW会計事務所でも相続税のシミュレーションを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。