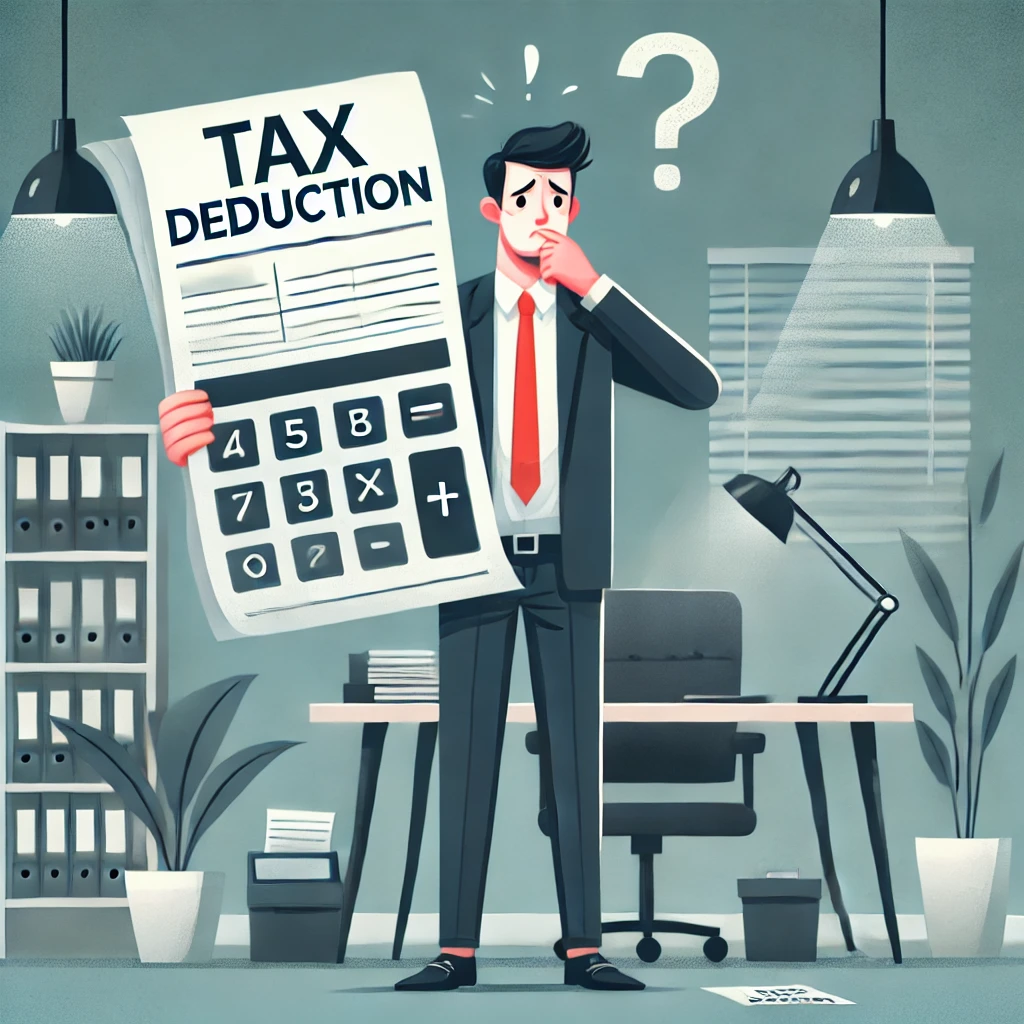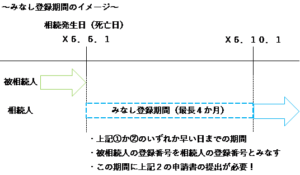拝啓 歳末の候、皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
仕事納め:2024年12月27日(金)
仕事始め:2025年1月6日(月)
期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、1月6日以降、順次対応いたします。
皆さまにはご不便をおかけしますが、どうぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
本年も格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
来年もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
皆さまにとって新しい年が、さらに素晴らしい飛躍の一年となりますようお祈り申し上げます。
敬具