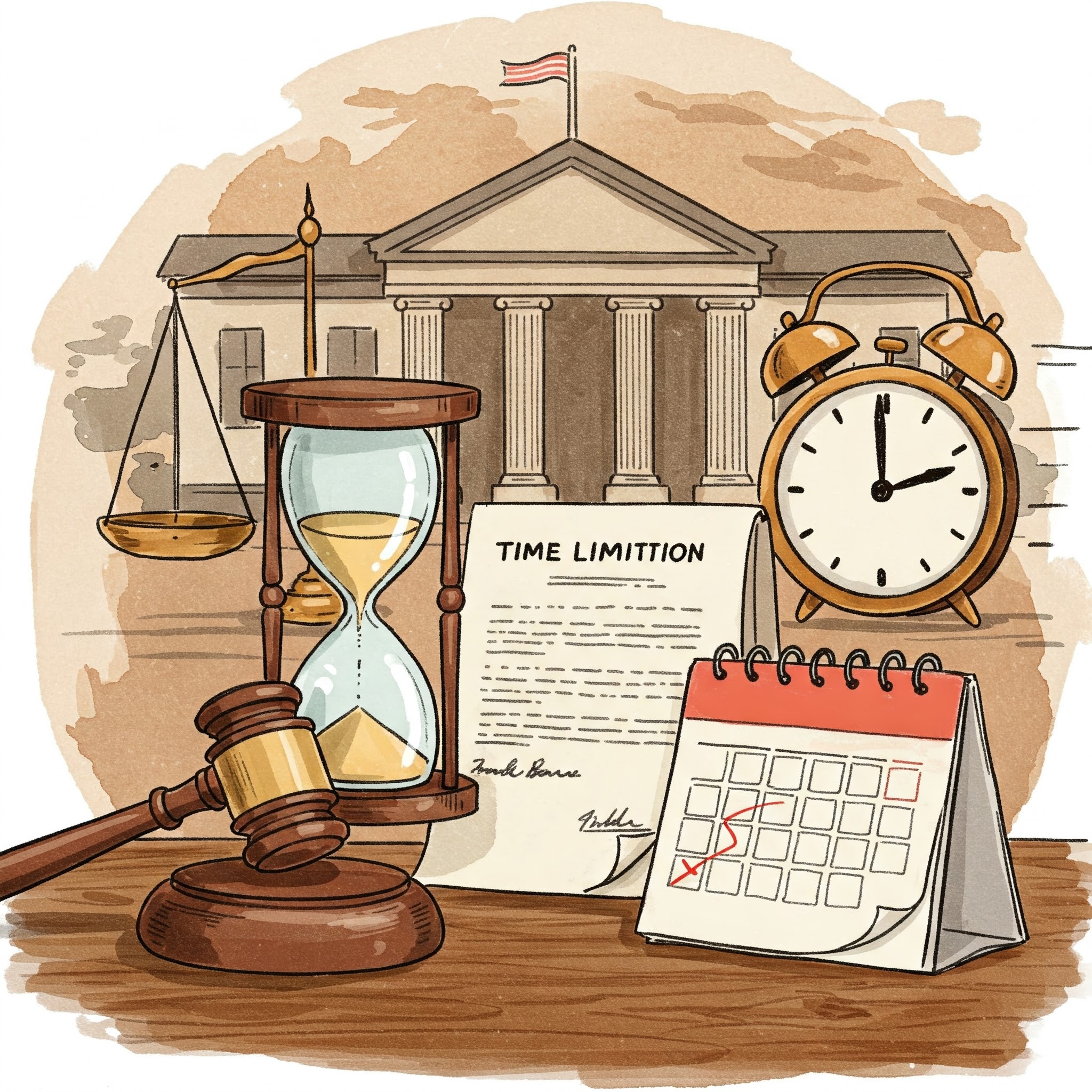こんにちは。 FLOW会計事務所の野澤です。
年が明け、あっという間にもう2月ですね。 税務の世界では、2月16日から始まる所得税の「確定申告」が一大イベントとして知られていますが、それより少し早くスタートする重要な手続きがあることをご存知でしょうか?
それは、「贈与税の申告」です。
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者(もらった人)の住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。所得税よりも受付開始が早く、すでにスタートしています。
「親から少し援助してもらったけれど、これって税金がかかるの?」 「贈与税はかからない金額だと聞いたけれど、申告しなくていいの?」
この時期、当事務所にもこうしたご相談が多く寄せられます。 そこで今回は、贈与税の申告が「必要な人」と「不要な人」の境界線について、分かりやすく解説します。
まずは基本の「基礎控除110万円」ルールを確認
贈与税の基本は、「1月1日から12月31日までの1年間」にもらった財産の合計額で判断します。原則として、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。
ここで注意したいのが、「もらった人(受贈者)ごとの合計」であるという点です。
父から100万円をもらった。
これだけなら110万円以下なのでセーフです。
しかし、もし同じ年に母からも50万円もらっていたとしたら?
父から100万円 + 母から50万円 = 合計150万円
この場合、110万円を超えた「40万円部分」に対して贈与税がかかるため、申告が必要になります。「あげた人ごと」ではなく、「もらった人の合計」で判定することを忘れないようにしましょう。
【贈与税申告が必要な人】
では、具体的にどんな人が申告会場(またはe-Tax)へ向かわなければならないのでしょうか。主なケースをまとめました。
1. 1年間の贈与額が110万円を超えた人 もらった人(受贈者)の合計
もっともシンプルなケースです。 現金だけでなく、株式、不動産、車などの価値も含めて計算します。110万円を超えた場合は、超えた分に対して課税されるため、申告と納税が必要です。
2. 「相続時精算課税制度」を初めて使う人
これは、「2,500万円までは贈与税がかからず、将来相続するときに精算する」という制度です。 「税金がかからないなら申告不要では?」と思われがちですが、この制度を利用するためには、「私はこの制度を使います」という届出(申告)が絶対に必要です。 申告を忘れると、通常の高い税率が適用されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
3. 「住宅取得等資金の非課税特例」を使う人
「親からマイホーム資金として500万円援助してもらった」といったケースです。 一定の要件を満たせば、贈与税が非課税になる特例があります。
誤解しがちなポイントなのですが、「特例を使って税金がゼロになる場合」でも、申告は必要です。 「特例の適用を受けるための申告」をして初めて、税金がゼロになる仕組みだからです。申告をしないと、特例が認められず高額な贈与税が発生することになります。
4. 「配偶者控除(おしどり贈与)」を使う人
結婚して20年以上の夫婦間で、自宅やその購入資金を贈与する場合、最高2,000万円まで控除できる特例です。 こちらも住宅資金同様、特例を受けるためには申告書を提出することが必須条件です。
【贈与税申告が不要な人】
次に、申告をしなくてよいケースです。
1. 1年間の贈与額が110万円以下の人 もらった人(受贈者)の合計
前述の通り、通常の贈与(暦年贈与)で、特例などを使わず単純に合計額が110万円以下であれば、申告は不要です。
2. 生活費や教育費として「必要な都度」受け取ったお金
例えば、親が大学生の子供に送る仕送り(家賃や生活費)、入学金などの教育費です。 これらは、通常必要と認められる範囲であれば、金額に関わらず非課税とされています。
重要なポイントは「必要な都度」であることと「通常必要と認められる範囲内」であることです。 「向こう4年分の生活費」として数百万をまとめてポンと渡してしまうと、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
【よくある勘違い・注意点】
申告の要・不要を判断する際、落とし穴になりやすいポイントをご紹介します。
保険金も「贈与」になることがある
「親が保険料を負担していた生命保険」の満期保険金を、子供が受け取った場合。これは「親から子供へ、保険金という形でお金が渡った」とみなされ、贈与税の対象になります(※契約形態によります)。 現金の手渡し以外も「みなし贈与」として課税されることがあるので注意しましょう。
借金の肩代わり
「子供の借金を親が代わりに返済した」という場合、その返済額相当を親から子供へ贈与したとみなされますので注意しましょう。
申告期間と手続き方法
2025年(令和7年)分の贈与税申告期間は以下の通りです。
期間:2026年(令和8年)2月2日(月)~3月16日(月)
最近では、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、スマホやパソコンからe-Taxで申告される方が増えています。税務署に行かずに自宅で完結できるため、非常に便利です。利用可能時間は国税庁のホームページから確認できます。
迷ったら専門家に相談を
贈与税の仕組みは、「特例を使うなら申告が必要」「生活費なら不要」など、少し複雑なルールになっています。
「自分は申告が必要ないと思っていたけれど、実は必要だった!」 という場合、後からペナルティ(無申告加算税など)がかかってしまうこともあります。
「自分のケースはどうなんだろう?」 少しでも迷われた際は、自己判断せずに、お近くの税務署や税理士にご相談されることをおすすめします。
当事務所でも、贈与税に関するご相談を承っております。 「難しい言葉は使わずに」ご説明することを心がけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。