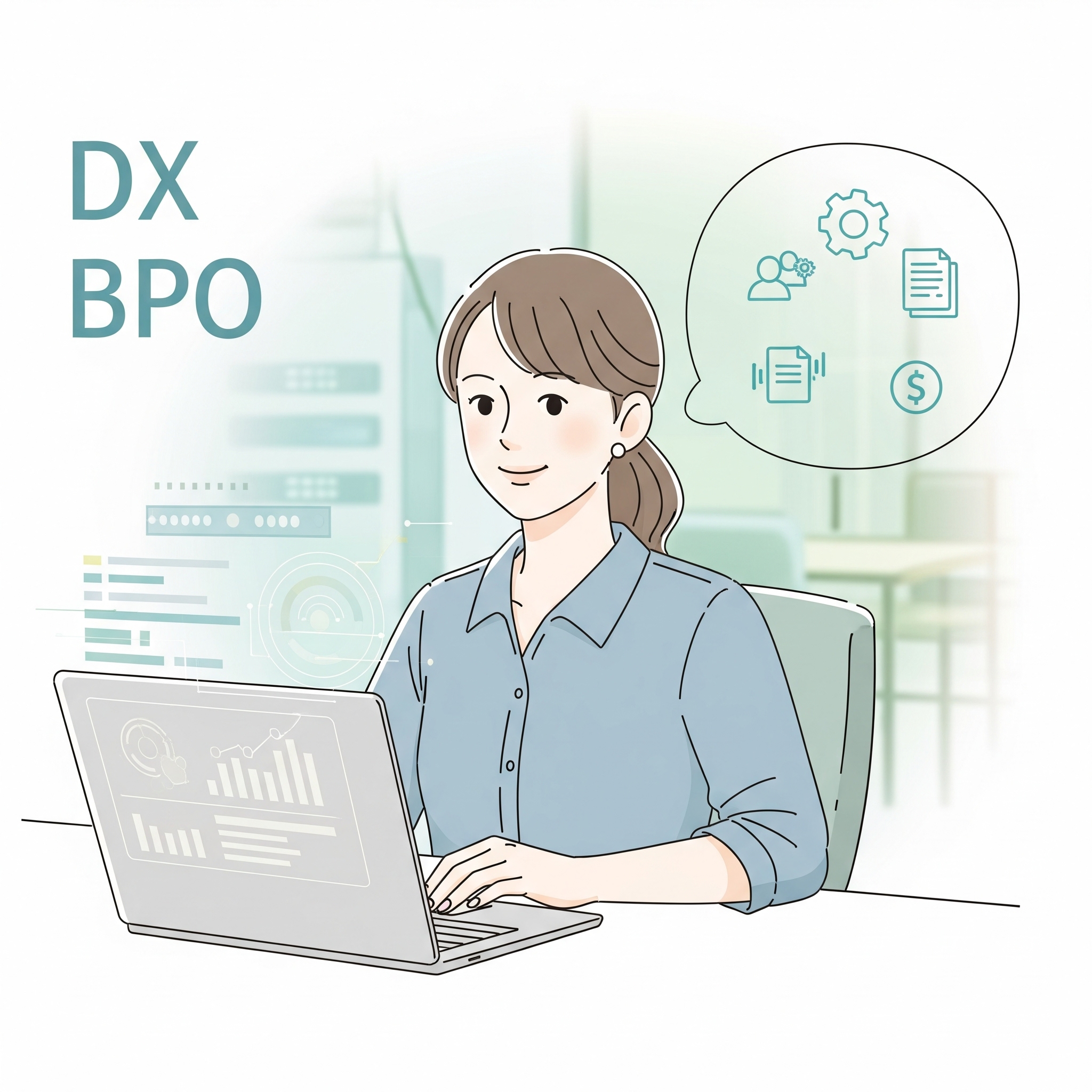こんにちは。会田です。 私たちは日々の業務の中で、お客様の事業が持続的に発展していくためのサポートをさせていただいています。事業の進め方を決定するためには、まず自社を取り巻く状況を客観的に把握することが不可欠です。
今回は、多くのビジネスオーナーやトップマネージャーに人気の高い、戦略計画の基礎となる分析手法「SWOT分析(スウォット分析)」について、その基本と具体的な活用法を分かりやすく解説します。
1. SWOT分析とは? その定義と必要性
SWOT分析は、事業戦略や経営計画の立案、意思決定をサポートするために広く活用されている手法です。SWOTとは、以下の4つの要素の頭文字を取った略語です。
Strengths(強み)
Weaknesses(弱み)
Opportunities(機会)
Threats(脅威)
この分析を行う真の目的は、現状の把握で終わるのではなく、分析結果を基に今後の事業の進め方や戦略を具体的に立てることです。そのため、データ収集はSWOT分析において重要な活動であり、収集された情報が事実に基づいたものになるほど、導き出される解決策はより現実的で信頼できるものになります。
2. 内部環境と外部環境の明確な区別
SWOTの4つの要素は、企業が「コントロールできるかどうか」という視点から、「内部環境」と「外部環境」に明確に分類されます。
内部環境:コントロール可能な要素(強みと弱み)
内部環境とは自社の状況を指し、企業が直接コントロールできる要素です。
・強み (S) – 内部のプラス面
組織に競争上の優位性をもたらす得意分野です。具体的には、熟練した従業員のスキル、効率的なプロセス、強固なブランド評判、高い技術力やノウハウ、財務能力などが含まれます。
・弱み (W) – 内部のマイナス面
組織が不足している、または課題に直面している部分です。例えば、古い技術、スキル不足、非効率なプロセス、財務実績の低さなどが該当します。弱みは改善の余地がある部分でもあります。
実践のポイント 内部環境(強みや弱み)を洗い出す際には、単なる感覚的な「思いつき」にならないよう、必ず競合他社との比較の中で、自社の優位性や劣っている点を具体的に評価することが極めて重要です。
外部環境:コントロールできない要素(機会と脅威)
外部環境とは市場や社会全体の状況を指し、自社が直接コントロールできない要因です。
・機会 (O) – 外部のプラス面
組織に有利に働く環境変化やトレンドです。市場の成長、顧客ニーズや嗜好の変化、法規制の緩和などがビジネス拡大のチャンスとなります。
・脅威 (T) – 外部のマイナス面
組織に不利に働くリスクや潜在的な危険性を指します。法規制の変更、経済の低迷、新しい競合企業の参入、物価高騰などが挙げられます。
実践のポイント 外部環境を分析する際は、ある一つの事柄が、見方によって「機会」にも「脅威」にもなり得ることに注意が必要です。外部環境の変化が自社にとってプラスとマイナスの両側面を検討し、整理することが大切です。
3. クロスSWOT分析で戦略を具体化する
4つの要素を洗い出した後、内部環境と外部環境の要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」に進むことで、具体的な事業戦略の方向性を導き出します。
強み × 機会(SO戦略:積極戦略)
自社の強みを最大限に活かし、市場の機会を利用して事業拡大を図るための「攻め」の戦略です。
例:高い技術力(S)を、成長している新規市場(O)に投入し、新製品を開発する。
弱み × 機会(WO戦略:改善戦略)
市場の機会を利用して、自社の弱みを克服したり改善したりする施策を検討します。
例:知名度の低さ(W)を、広がりつつあるSNSマーケティング(O)を活用して改善する。
強み × 脅威(ST戦略:差別化戦略/対抗戦略)
自社の強みを活用することで、外部からの脅威の影響をかわしたり、競合他社と差別化を図ったりする「守り」の戦略です。
例:強固なブランド力(S)を活かし、低価格競争を仕掛けてくる競合(T)に対し、価格以外のプレミアムな価値を訴求する。
弱み × 脅威(WT戦略:防衛戦略/撤退戦略)
弱みを抱えた上で、脅威の悪影響を最小限に抑えるための対策(事業の縮小や撤退を含む)を検討します。危機回避を最優先します。
例:資金力の弱さ(W)と、原料の高騰(T)に対し、在庫を最小限に抑え、採算の合わない事業から撤退する。
このクロス分析を行うことで、戦略の道筋がより具体的になり、「どの施策に経営資源を集中すべきか」が見えてきます。
4. 成功のための実践的なヒント
SWOT分析を成功させ、事業に役立てるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
目的を明確にする: 分析を始める前に、「この分析によってどのような目的を達成したいのか」を明確に定義しておくことで、ビジョン達成に向けた戦略立案が効果的になります。
客観性を確保する: 内部環境の分析は特に主観的になりがちです。思い込みを排し、できる限りデータや事実に基づき分析を行うことが重要です。経営者やボードメンバーだけでなく、従業員、顧客など様々な関係者の意見を取り入れることも、客観的な分析に繋がります。
セグメントを分ける: 企業に複数の事業がある場合は、全てを一緒にする「経営総合SWOT分析」ではなく、商材別、顧客属性別、事業部別などに分けて分析することで、より具体的で効果的な戦略を導き出せます。
定期的に見直す: SWOT分析は一度作って満足するものではありません。内部環境も外部環境も経営を続けていく上で刻々と変化していくため、戦略の基盤として定期的な見直しを行うことが大切です。
まとめ
SWOT分析は、自社の強みを最大限に生かし、潜在的なリスクや課題に対応できる戦略を立てるための重要なフレームワークです。
私たちは、皆様が事業における機会を逃さずに掴み、持続的に成長していくための経営計画をサポートしたいと考えております。
ご自身の事業を客観的に分析することや、分析結果を具体的な戦略に落とし込むことにお困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。