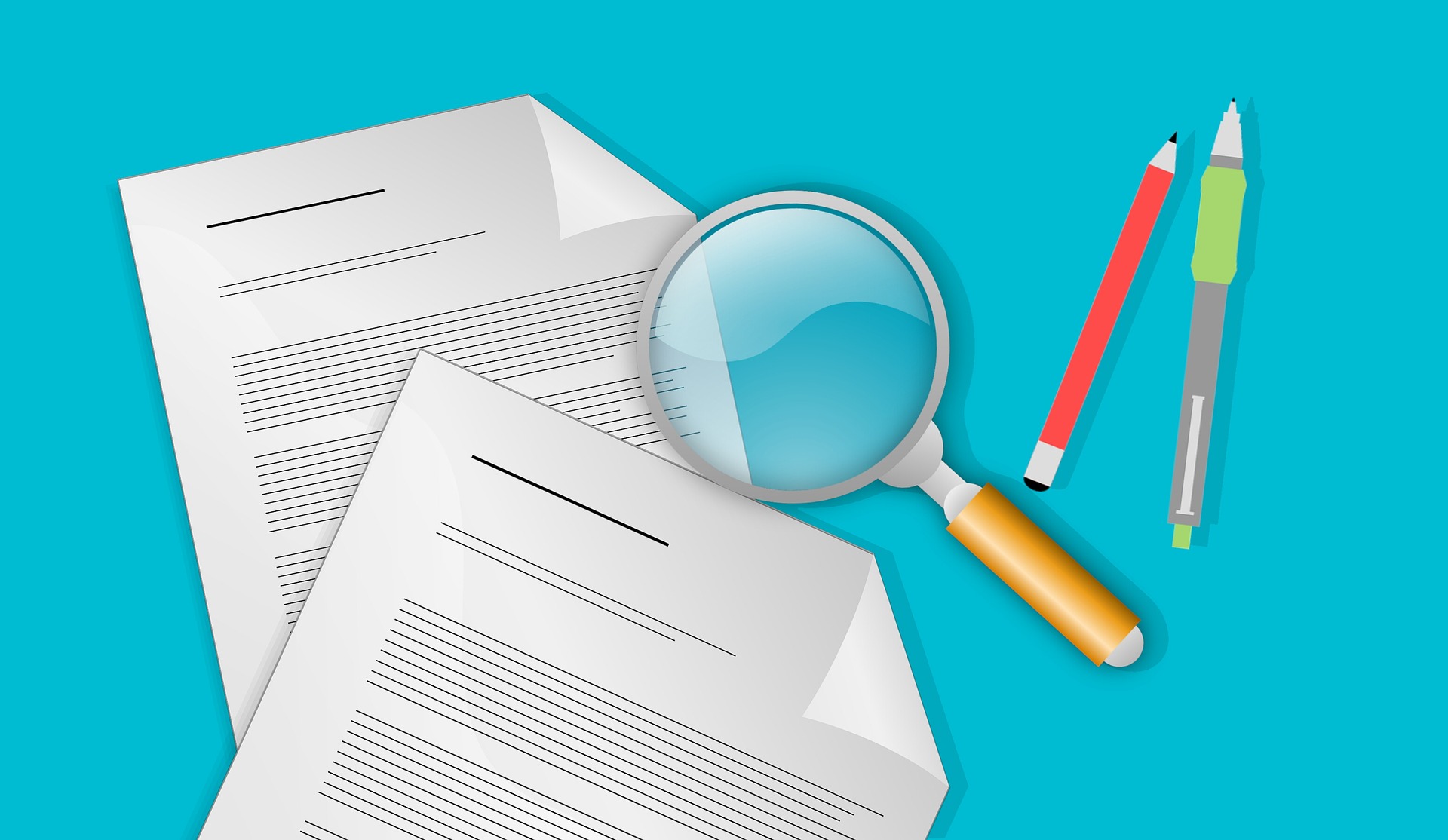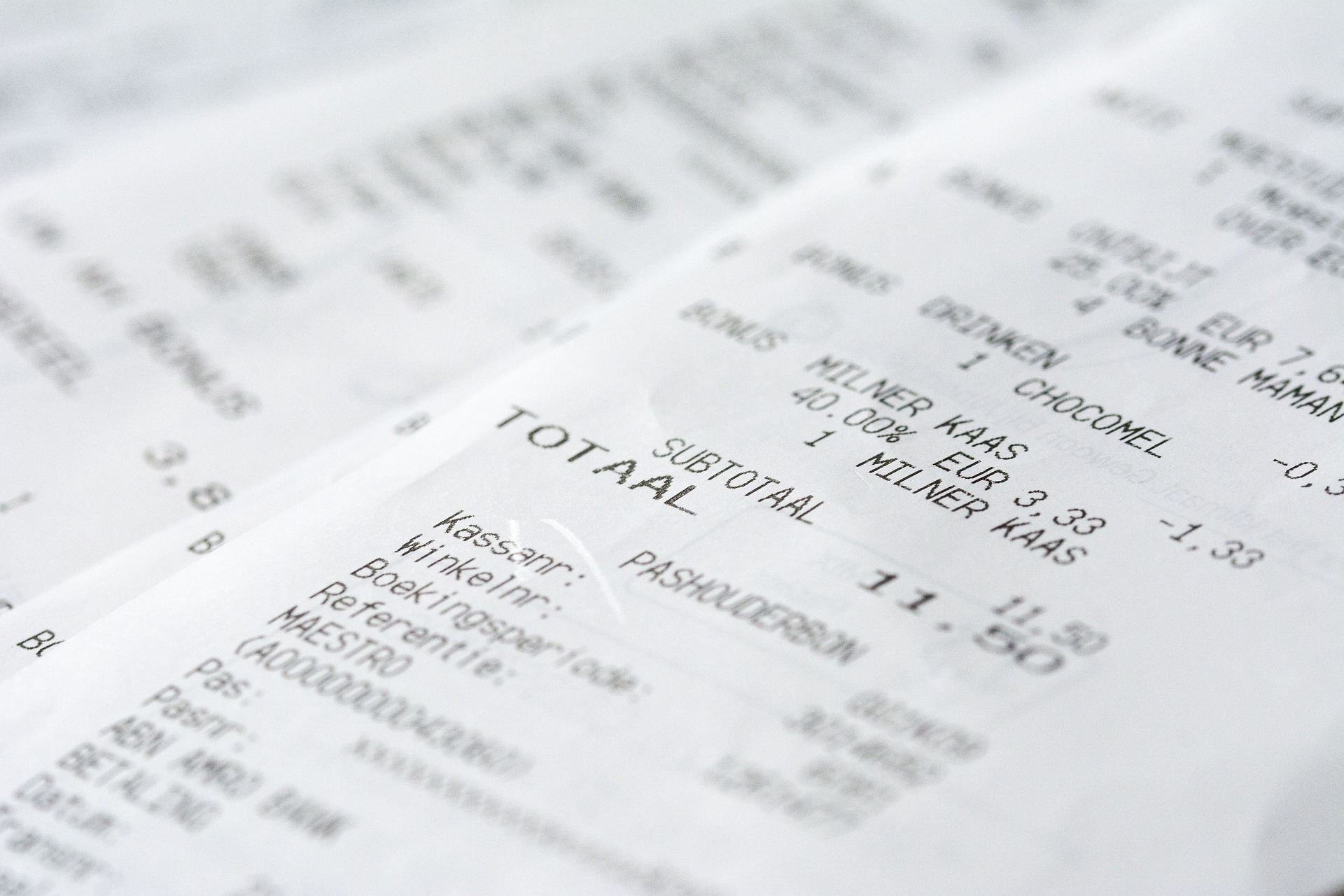【口座振替のインボイスについて】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、口座振替によって決済される家賃等についてのインボイスの取り扱いについてシンプルに解説します。
結論からお伝えすると、「登録番号などの必要事項が記載された契約書」と「日付と金額が印字された通帳」を保存しておけば、インボイスの発行は省略が可能です。
また、令和5年9月30日以前の契約書については、登録番号などの不足している情報を記載した書類を作成して保存すれば改めて契約書を作成する必要はありません。
契約書を一から作成しなおすのはとても大変ですから、こちらの方法で代替するのが現実的ですね。
なお、「登録番号などの必要事項が記載された契約書」と「日付と金額が印字された通帳」にはそれぞれ下記のことが記載されている必要があります。
◇登録番号などの必要事項が記載された契約書
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③取引内容
④取引金額に対する消費税額と適用税率
⑤請求書等受領者の氏名又は名称
登録番号と税率は今までの契約書には記載されることはあまりありませんでしたので、忘れないように注意です。
◇日付と金額が印字された通帳
①取引年月日
②税率区分ごとに合計した取引金額
通帳に関してはもともと①②の内容は記載されているはずなので、特段何かを準備いただくことはなさそうですね。
以上、簡単ですが、口座振替の場合のインボイスの取り扱いについてでした。
少しでも参考になれば幸いです!