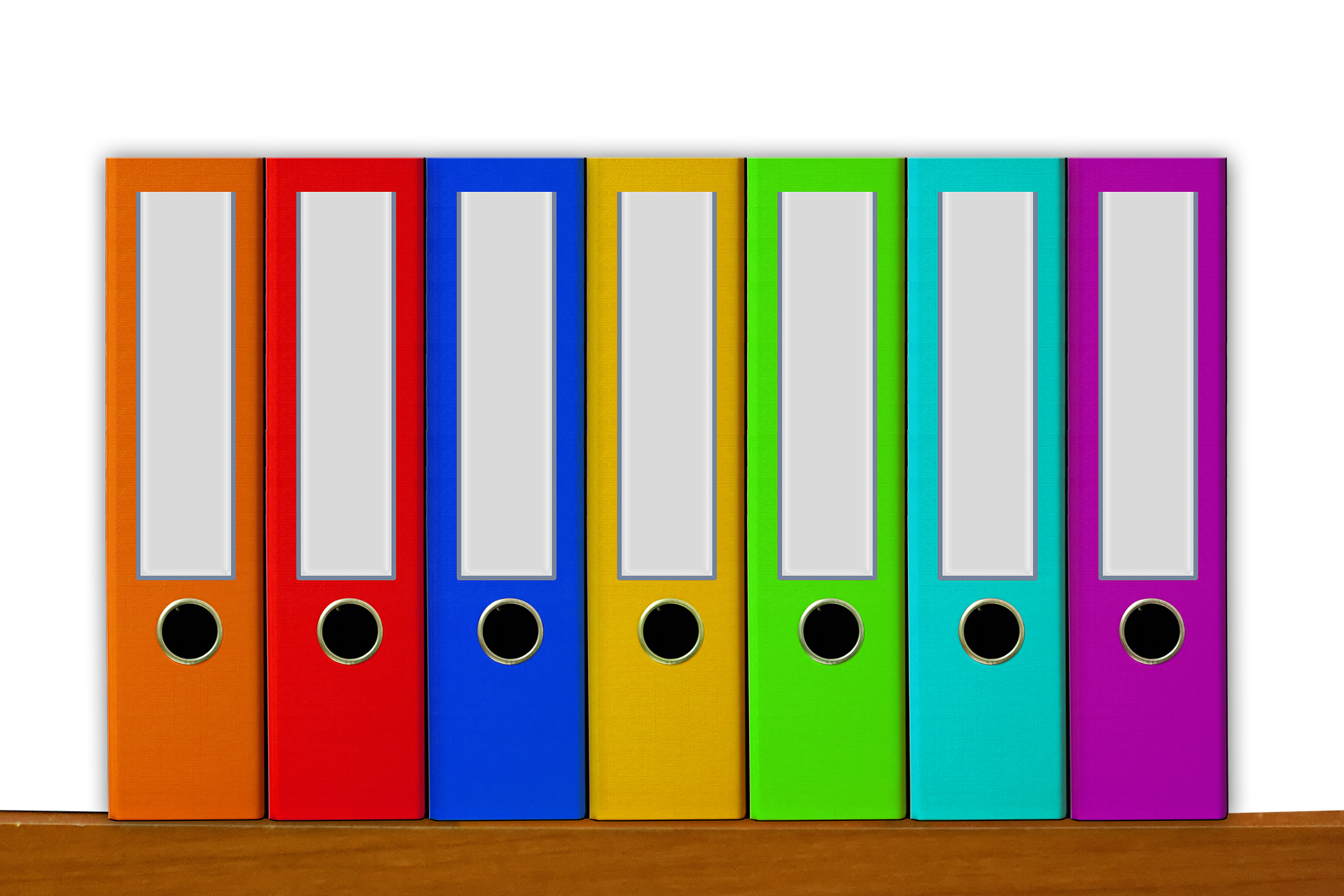【インボイス制度の準備って何をすれば?】
日ごろお客様と接していて感じることですが、だいじな話なのになんだか浸透していないんですよねえ、インボイス制度。
売上に消費税を加えて請求書を作成している皆さん!
皆さん全員に関係のある話ですよ~。
来年の令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
準備は大丈夫でしょうか?
なんだか未だにモヤモヤ・・・としている方のために、大まかにお話しますね!
Qインボイス制度って何?
インボイスとは「適格請求書」のこと。
今までは、請求書・領収証・レシートの形式を問わず、課税商品を仕入れたら(購入したら)消費税を払ったものとして扱えました。ところが、これからは、適格請求書(インボイス)でないと、支払消費税(仮払消費税)を控除できなくなるのです。
*消費税の基本的なイメージ
消費税は売上があったときに10%の消費税を計上してお客さまに請求します(=預かった消費税)。
逆に何か購入するときや仕入をするときには支払金額に消費税が加算されています(=支払った消費税)。
「預かった消費税△支払った消費税=あなたが納税する消費税」になります。
このとき、購入先がインボイスに準拠していない場合、あなたは支払った消費税を控除できなくなってしまうんです…
例で見てみましょう。
例)税込売上110万円(預かった消費税10万円)・税込仕入55万円(支払った消費税5万円)があった場合にあなたが支払う消費税
①インボイスあり
預かった消費税10万円△支払った消費税5万円=あなたが納税する消費税5万円
②インボイスなし
預かった消費税10万円△支払った消費税0円=あなたが納税する消費税10万円
おわかりでしょうか…
購入先がインボイスに準拠していないと、支払った消費税があっても納税する消費税が増えてしまうのです…
あなたはインボイスに準拠していない取引先と取引できますでしょうか…
逆もしかりで、あなたのお客さまもあなたがインボイスに準拠しているかどうか気にすることになります。
この制度が、インボイス制度。
「適格請求書(インボイス)」には、消費税に関して今までよりも詳しい記載が求められています。
事前に事業者登録をして、登録番号をとることも必要です。
得意先にインボイスを求められたときのため、そろそろご準備を!
Q「適格請求書」って何?今までの請求書や領収証ではダメなの?
適格請求書とは請求書だけでなく領収証、レシート等も含みます。
次の記載が必要です。
1適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2取引年月日
3取引内容(軽減税率の対象品目があればその旨)
4税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
5消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
6書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
うわー大変そう!と思われたかもしれませんが、今までと変わったのは赤の3か所くらいです。
とはいえ、
- 登録番号をとる
- 請求書・領収証のフォームの手直し(4,5に合うように直す、登録番号を入れる)
といった準備が要りますね。
登録番号の追加だけだから、ウチはゴム印を作って押すよ!というお客様もいました。
それも一つの方法ですね。
【ご注意】消費税の免税事業者のかたは、登録番号を申請すると、令和5年10月1日から消費税の課税事業者になり、消費税を納めなくてはならなくなります。
Q登録番号を取らない、適格請求書もめんどうだから作りたくない場合は?
適格請求書発行事業者の登録は任意なので、登録しなくても良いのです。
登録が無ければ、適格請求書を発行する必要もありません。(というか、登録した事業者しか適格請求書は発行できません。)
ただ、適格請求書を発行しない事業者からの購入は、買い手側(得意先)にとっては
・納税額が増える(上記例の通り)
・仮払消費税の有無を確認する手間がかかり、経理処理がたいへんになる
等デメリットが多いので、取引を敬遠される、消費税分の値下げを要求されるなどの恐れがあると言われています。
(実際、取引を控えたいという声も聞きました)
いっぽう、得意先が一般のお客さんなど消費税の納税が関係ない人であれば得意先に不利益は無いので、適格請求書を求められることは無いでしょう。
得意先から適格請求書を求められることが無いなら、事業者登録も不要です。
特に、あなたが消費税の免税事業者の場合は、免税を続けられますので登録しないほうがおトクです。
得意先の対応を確認してから、インボイス制度を考えても良いと思います!
確実にやってくる話なので、準備して備えましょう!
***最後までお読みくださって、ありがとうございました!(⌒∇⌒)/斉藤***