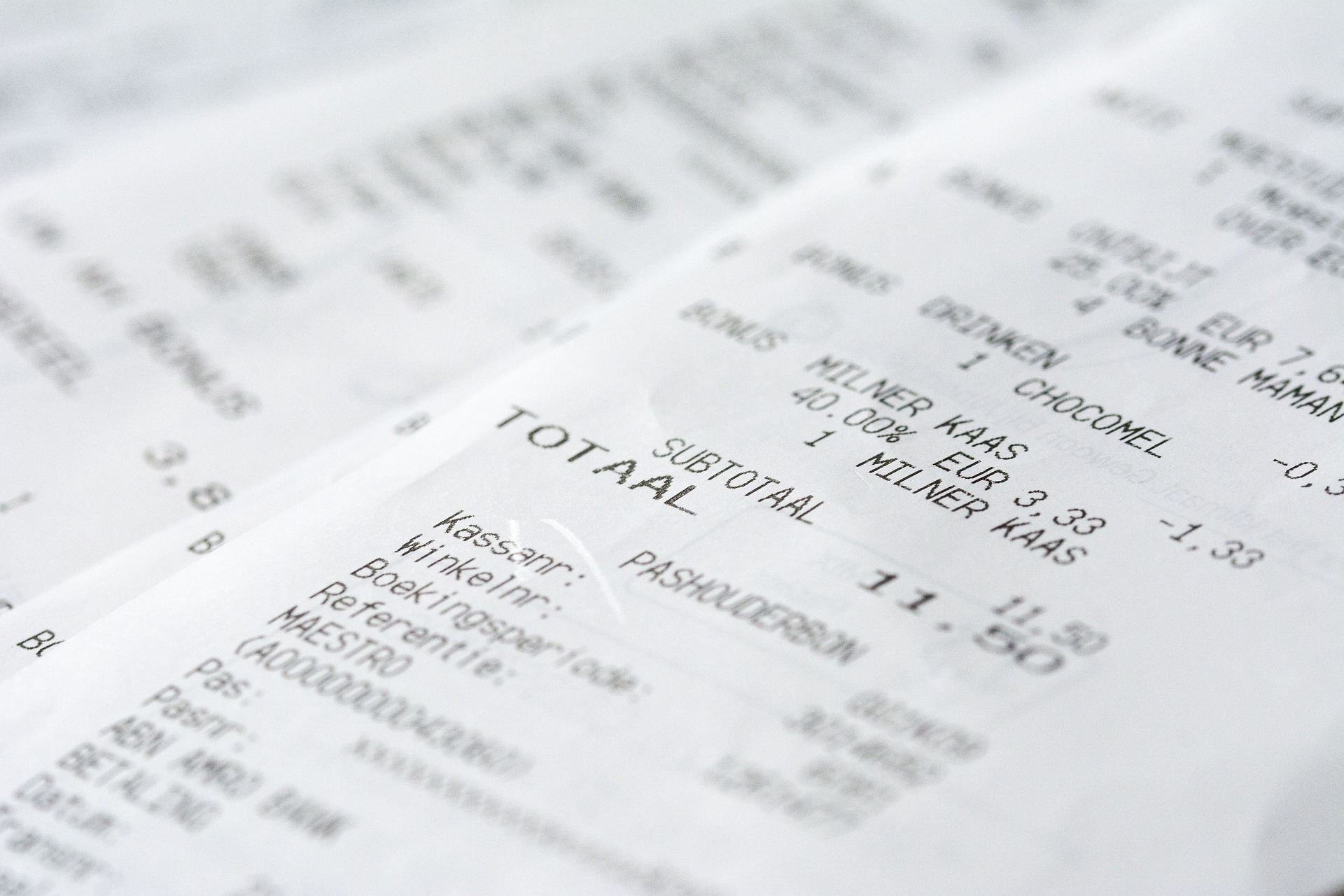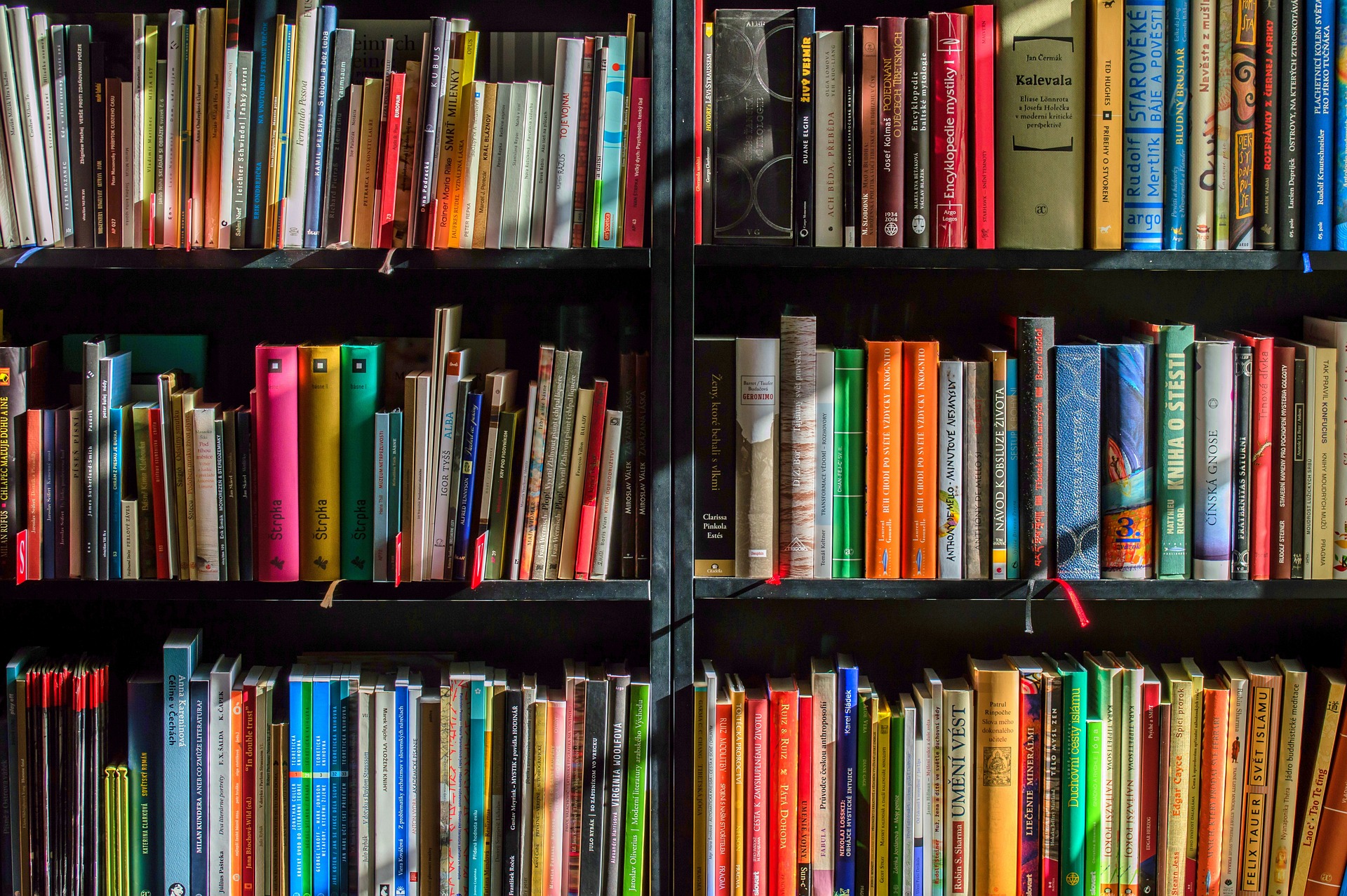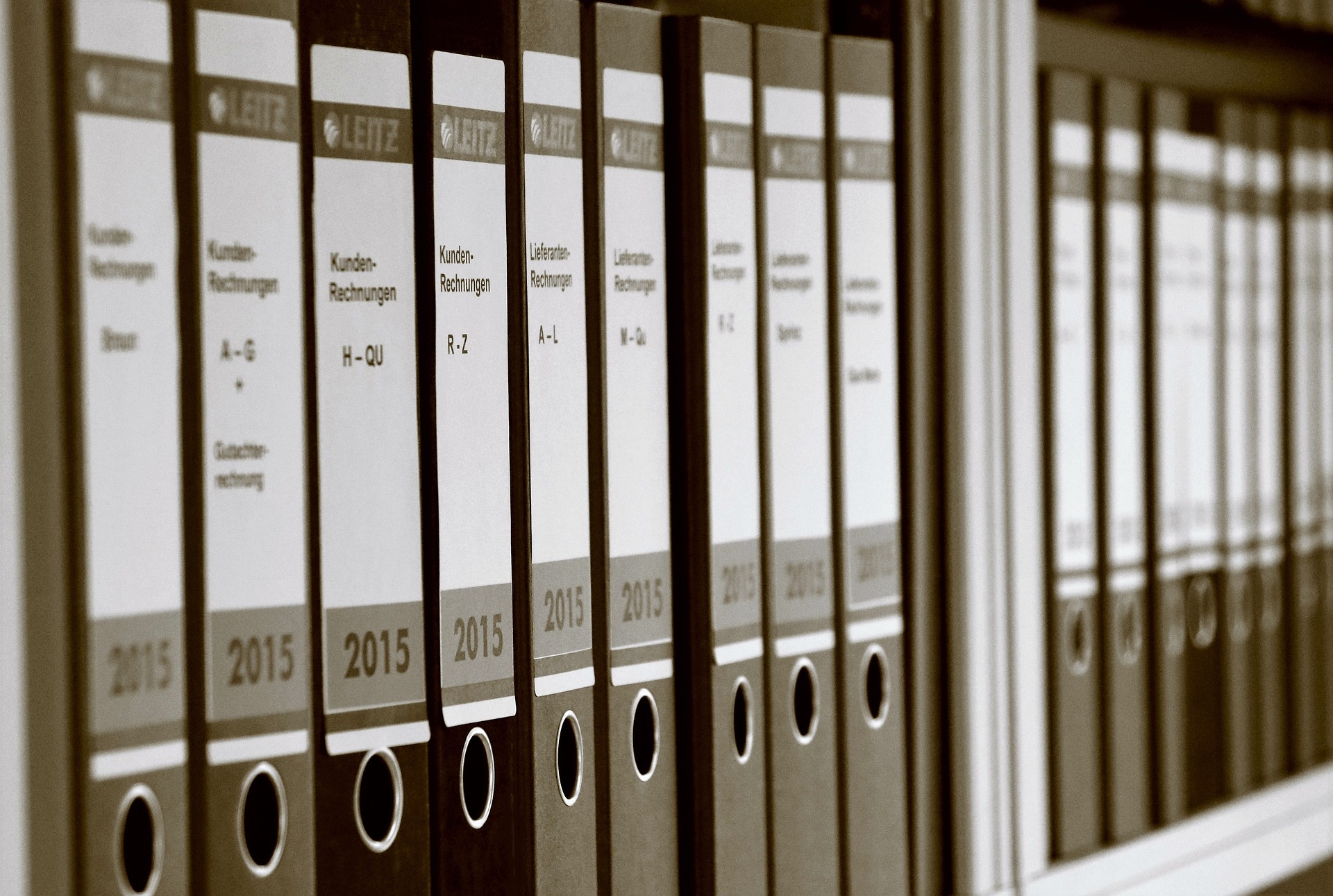【売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!】
税理士法人FLOW会計事務所です!
令和5年10月からスタートするインボイス制度ですが、「インボイスの保存」が仕入税額控除の要件となっておりました。
しかし、期間限定で下記の緩和措置が取られることになりました。
課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下である事業者については、インボイス制度から6年間、支払対価の額が1万円未満(1取引単位)の課税仕入れについて、インボイスの保存は不要。
◇対象期間
令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の課税仕入れ
◇対象者
・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者
・特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者
*基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は全事業年度開始の日以後6か月間の期間の課税売上高が5000万円以下である場合は特例の対象
◇まとめ
結論としては「一定の事業者は1万円未満のインボイスは保存不要」という改正になるのですが、個人的にはあんまり効果がない改正のような気がしています…
というのも、わざわざ「一万円未満かな?どうかな?」なんてインボイス見て判断するの面倒じゃないですか…そんな判断する時間も惜しいので最初から全て保存した方がラクなんじゃないかなと個人的には感じてしまいますね…
ただ、情報として知っておいて損はないかとは思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!