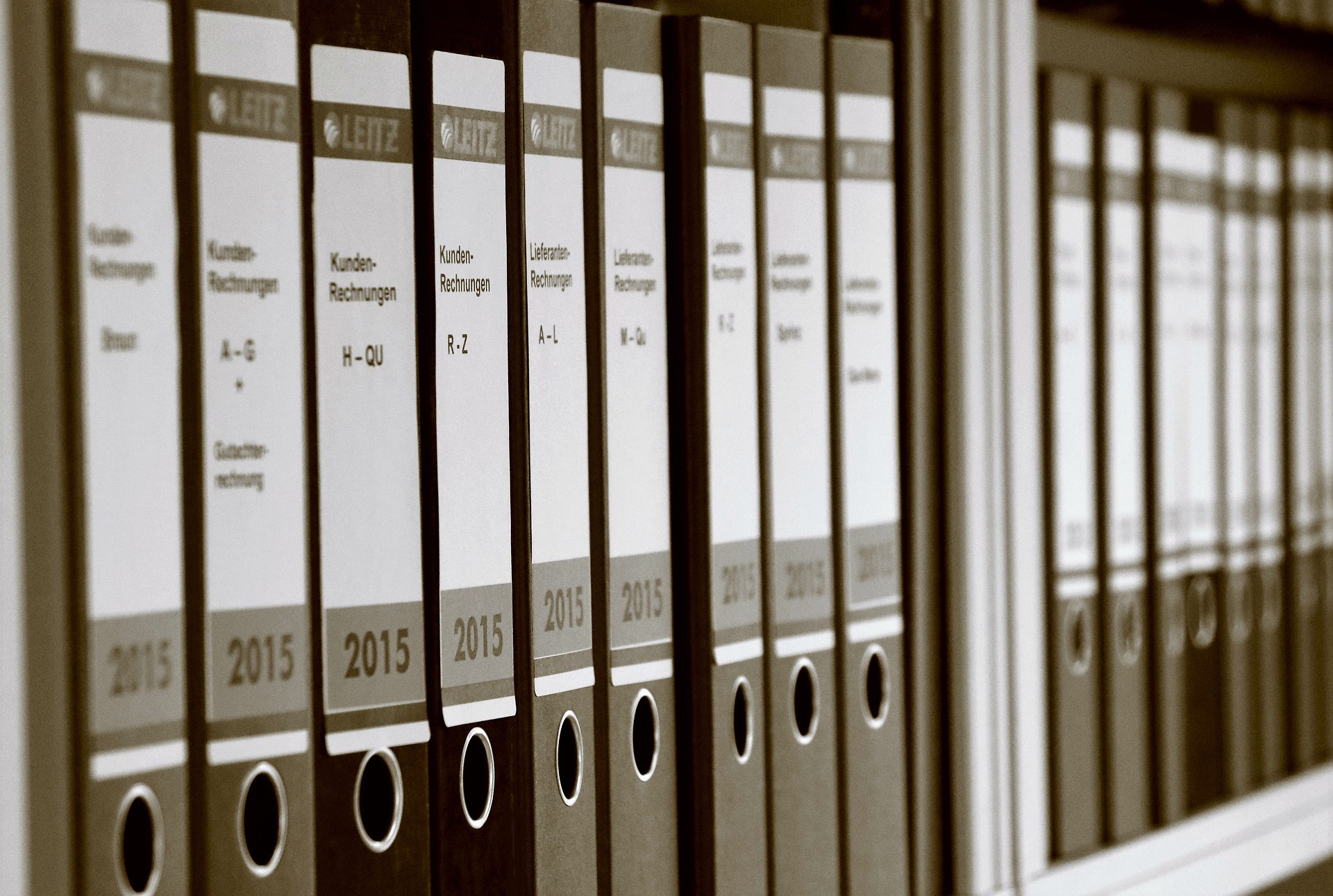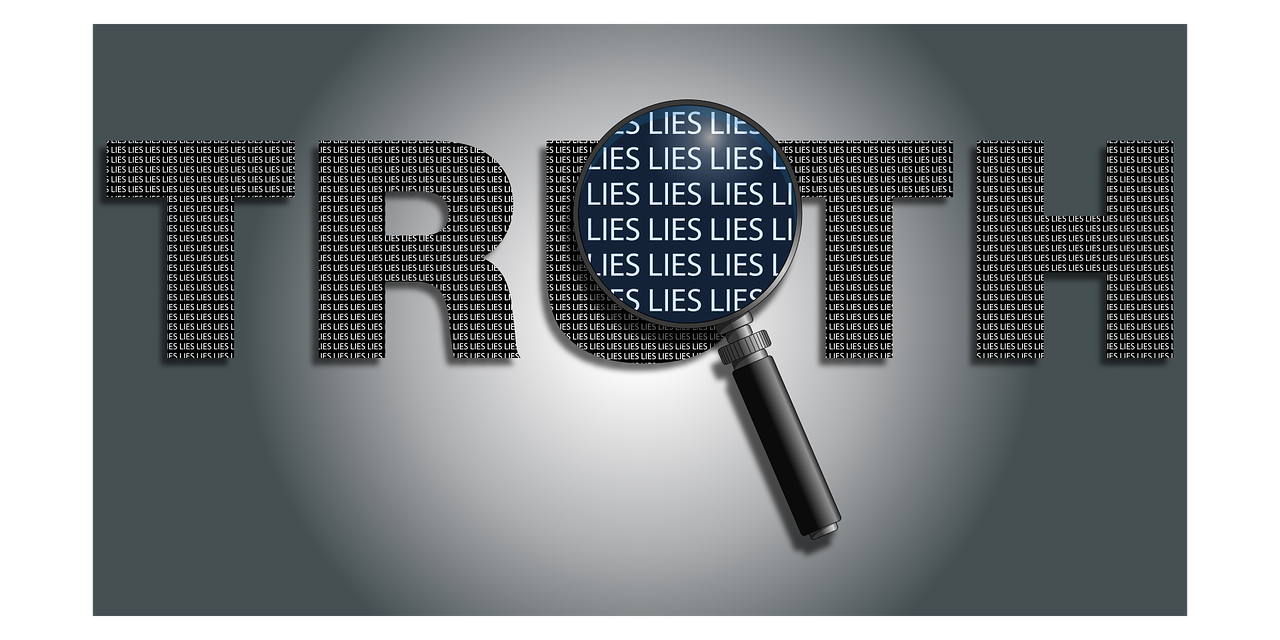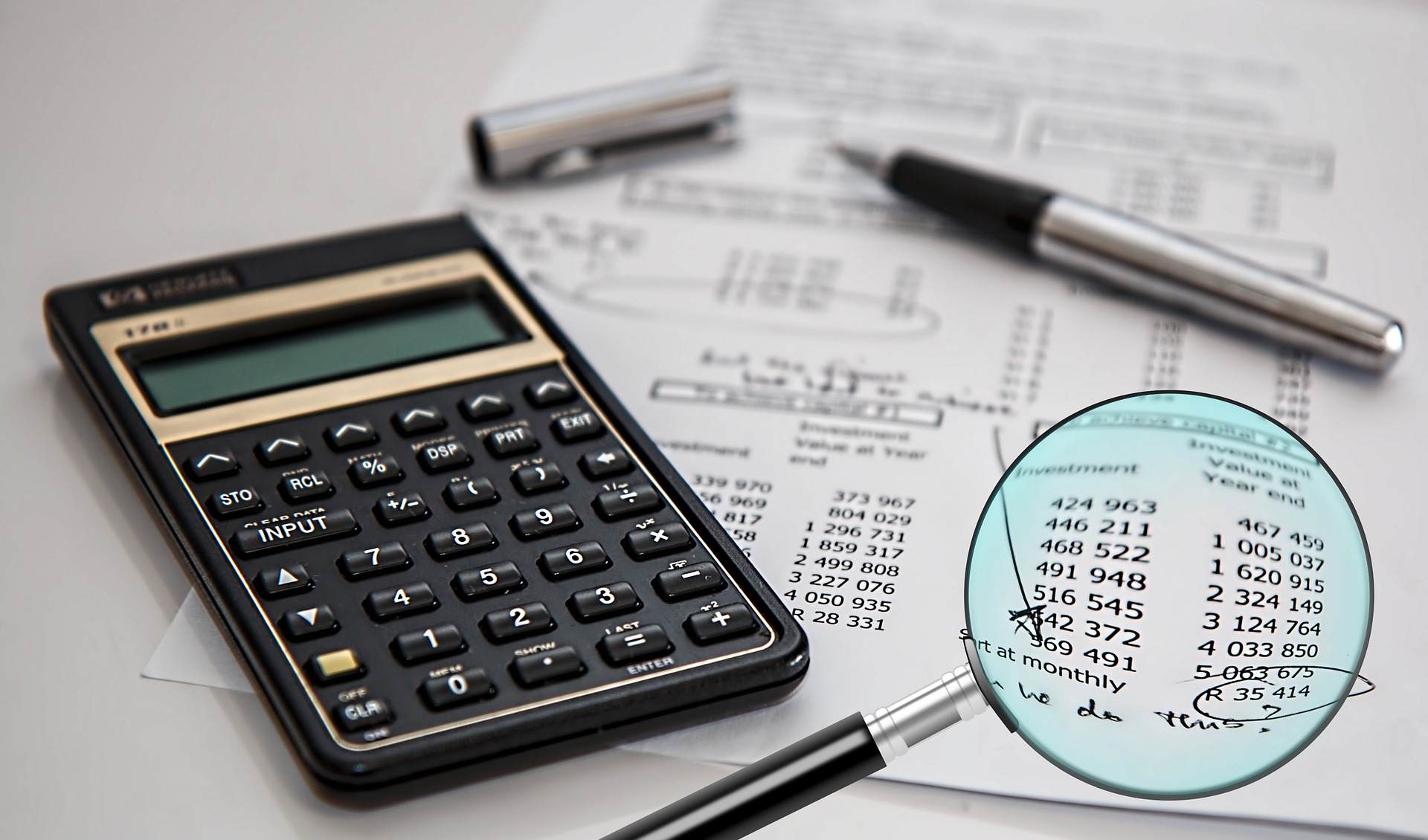こんにちは、税理士法人FLOW会計事務所の野澤です。
相続は、残されたご家族の生活に直結する重要な問題です。単なる節税ではなく「スムーズな納税」と「平穏な生活の継続」を最優先に考えた対策が求められます。今回は、皆様が後悔しないために特に重要な論点である「名義預金」と「生命保険」、そして最も大切な「現金」の役割について解説いたします。
1. 「名義預金」
相続が発生し、後に税務調査が入った際に必ずと言っていいほど確認されるのが「名義預金」の存在です。
名義預金とは、口座名義人(子など)と、実際に資金を拠出し管理していた人(親など)が異なる預金のことです。親が子名義で口座を開設し資金を管理していた場合、子は「もらった」つもりでも、親の相続財産とみなされる可能性があります。
名義預金とされるリスクとその背景
なぜ税務署は相続税の税務調査で、名義預金を確認するのでしょうか。贈与税には原則6年(悪質な場合は7年)の時効があります。しかし、名義預金となれば親の相続財産となり、何十年前に遡っても相続財産として相続税が課税されます。故人だけでなく、家族の過去10年程度の預金移動も調査し、贈与の事実を証明できない場合には、親の相続財産とみなされ名義預金として指摘をうける可能性があります。
贈与の立証責任
正式な贈与(あげる側ともらう側の合意があった)場合でも、口頭の合意だけでは税務調査で認めてもらうのは非常に困難です。
名義預金と指摘されないための重要な対策
贈与の都度、贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者が署名・押印し、保管しておくことが重要な証拠になります。
現金手渡しではなく銀行振込を利用することで、いつ、誰から誰へ、いくら資金が移動したか、客観的な記録も残しましょう。
また、通帳、印鑑、キャッシュカードを名義人(子など)自身が管理し、実際に預金を引き出したり、クレジットカードの引き落としに使うなど、名義人が口座を自由に利用している形跡を残すことも重要です。
2. 「生命保険金」
生命保険金には、(500万円 ×法定相続人の数)という非課税枠が設けられており、相続税対策としても非常に有効です。受取人を決める際には、「税務上の理屈」と「現実的な生活」のバランスが重要です。
税務上の理屈・配偶者の税額軽減との関係
配偶者には「配偶者の税額軽減」という大きな特例があり、1億6000万円まで、または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税はかかりません。相続が発生しても配偶者が安心して生活ができるよう定められているからです。
※但し、この特例は、法律上の配偶者であること、相続税の申告期限までに遺産分割されていること、相続税の申告を行うこと、が要件となります。
この特例を考慮すると、貴重な生命保険の非課税枠を、相続税がかかりにくい配偶者に使うのは「税務上はもったいない」という理屈が成り立ちます。
現実的な生活・納税資金・生活資金の確保
しかし、生命保険の最大の目的、メリットは、亡くなった後の配偶者の生活資金をすぐに確保できることです。
生命保険金は、原則として受取人の固有財産であり、遺産分割協議を待たずに、比較的迅速に現金として受け取ることができます。
結論として、多少税金が高くなっても、配偶者が安心して生活を立て直せるよう、必要な生活資金・納税資金として確保するという選択が、ご家族の安心につながる最良の対策です。
3. 「現金」の確保
相続税の滞納が増加する最大の原因は、相続財産の約4割以上を占める不動産といわれています。不動産は評価額を下げることができ、節税対策としても有効な面がある一方で、相続税の納税は原則、現金一括納付が求められます。
現金不足が招く深刻な事態
・納税資金の不足
財産をすべて不動産に変えてしまうと、納税資金を捻出できないことで申告期限(10ヶ月以内)までに不動産を売却する必要に迫られます。
・ペナルティの発生
期限までに売却できなければ納税も遅れるため、延滞税などのペナルティが発生します。最悪の場合、自己破産に至るケースもあります。
・遺産分割のトラブル
不動産は分割が難しく、公平な遺産分割ができないため、相続人同士の争いにもつながりやすいです。
現金こそがご家族を守る「一番の相続対策」です。 不動産を所有する場合でも、配偶者の生活資金や納税資金をまかなえるだけの流動性の高い現金や預貯金を必ず残しておくことが、最も確実かつ平和的な相続対策となります。
◆専門家へのご相談を
「相続」は、おそらく一生に一度の経験であり、知識がないために後で大きなトラブルに見舞われる方が少なくありません。特に不動産の評価(固定資産税評価額とは異なる)や、相続人の間の分割協議がまとまらない場合の納税(連帯納付義務)など、専門的な対応が必要になる場面が多いです。
事前に専門家にご相談いただくことで、ご家族にとって最善かつ平和な選択を導き出すことができます。
相続にご不安がある方は一度FLOWにご相談ください!